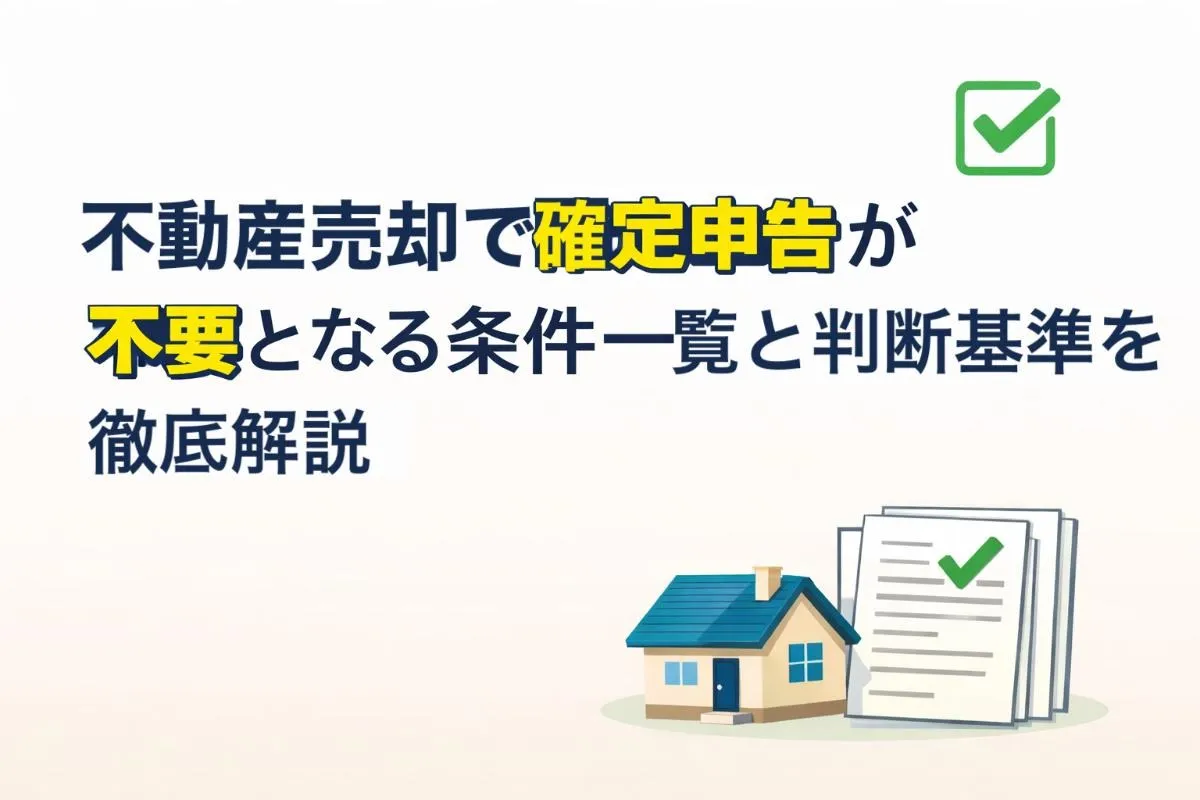家売却で確定申告が必要なケースと不要な条件や書類一覧を徹底ガイド
2025/09/12
家を売却した後の「確定申告」、実は多くの方が見落としがちなポイントです。特に【3,000万円控除】や【譲渡所得】の計算、さらには必要書類の準備・保存期間など、手続きが複雑で「何から始めればいいのか分からない」と悩んでいませんか?
不動産の売却後に確定申告が必要となるケースは、毎年数十万件に上るというデータもあります。売却益が出た場合はもちろん、損失が出ても申告で節税が可能な場合も多く、きちんと手続きしないと追徴課税やペナルティが発生するリスクも。放置すると数十万円単位の損失につながることも少なくありません。
本記事では、【売買契約書】【登記簿謄本】【取得費用の領収書】などの必須書類の一覧・取得方法から、申告義務の有無、手続きの流れ、節税に直結する特例制度まで、初心者でも迷わず進められるように徹底解説します。
「確定申告の準備、何をすればいいの?」という方も、この記事を最後まで読むことで、安心して家売却後の手続きを進めることができます。
目次
家売却で確定申告が必要なケースと不要なケースの判定基準
家を売却した場合、確定申告が必要かどうかは譲渡所得の有無や売却した不動産の種類、金額によって異なります。特に居住用財産の売却では、特例や控除が適用されるケースも多く、正しい判定が重要です。以下の表で主な判定基準を整理します。
| 判定項目 | 必要な場合の例 | 不要な場合の例 |
|---|---|---|
| 利益(譲渡所得)発生 | 売却益があり課税対象となる場合 | 損失や利益ゼロの場合 |
| 3000万円控除適用 | 控除を利用し利益がゼロ以下になる場合も申告が必要 | 売却益が出なかった場合 |
| 相続・贈与物件 | 相続や贈与により取得した不動産の売却 | 相続税申告のみで済む場合 |
| 不動産の種類 | マイホーム、土地、投資用物件など | 非課税財産(例:車庫のみ) |
正確な判定には、売却に関わる各条件を確認することが大切です。
家売却 確定申告 必要書類や条件 - 申告義務の発生条件と譲渡所得の計算基準
家売却で確定申告が必要となる場合、必要書類と条件を網羅的に準備することが求められます。主な必要書類と条件は以下の通りです。
- 売買契約書
- 登記事項証明書
- 譲渡所得の計算明細書
- 取得費の証明書(購入時の契約書やリフォーム費用の領収書等)
- 住民票(マイホームの場合)
- 3000万円控除を申請する場合は特例適用申請書
譲渡所得の計算は「売却価格-取得費-譲渡費用」で算出されます。売却にかかった諸費用(仲介手数料、測量費等)も控除対象です。適正な計算と証拠書類の保存が重要となります。
家売却 確定申告 不要なケース - 所得金額や譲渡所得が一定以下の申告不要パターン
家の売却で確定申告が不要となる主なケースは以下の通りです。
- 売却による譲渡所得が発生しない場合(取得費や経費が売却価格を上回る)
- 3000万円控除を利用し、譲渡所得がゼロ以下となった場合
- 相続税の申告のみで済むケース
また、投資用不動産や非課税財産の売却も申告が不要となることがあります。自身のケースが該当するかどうかは、国税庁のガイドや税理士への確認が安心です。
家売却 確定申告 いくらから必要か - 譲渡所得の計算方法と課税対象となる金額の具体的な目安
家売却で確定申告が必要となる目安は「譲渡所得がプラスになった場合」です。具体的には、以下の計算式で求めます。
- 譲渡所得 = 売却価格 -(取得費+譲渡費用)
- ここから特別控除(例:3000万円控除)を差し引く
譲渡所得がゼロを超える金額となれば、確定申告が必要です。計算例として、売却価格3000万円、取得費1800万円、諸経費200万円、控除3000万円の場合は課税所得はゼロとなります。課税対象となる金額はケースにより大きく異なりますので、計算シミュレーションも活用してください。
家売却 確定申告 しない場合のリスク - 期限遅延や申告漏れによるペナルティ
確定申告が必要なケースで申告をしないと、以下のようなリスクが発生します。
- 無申告加算税や延滞税の発生
- 最大20%の追徴課税
- 税務調査による過去分の遡及請求
- 特例・控除の適用不可
実際に、申告忘れにより数十万円以上の追徴課税を課された事例もあります。確定申告の期限(通常は翌年の2月16日~3月15日)を守り、必要な手続きを必ず行いましょう。
家売却の確定申告に必要な書類一覧と取得方法 - 書類の種類・入手先・保管期間
家売却 確定申告 必要書類の全リスト - 売買契約書、登記簿謄本、領収書など必須書類
家を売却した際の確定申告では、多くの書類が必要となります。以下に主要な書類を一覧でまとめます。
| 書類名 | 主な内容・用途 | 必要性 |
|---|---|---|
| 売買契約書 | 売却金額や売却日など基本情報の証明 | 必須 |
| 登記事項証明書(登記簿謄本) | 所有者や物件情報の確認 | 必須 |
| 取得時の契約書 | 購入時の価格や条件の確認 | 必須 |
| 譲渡所得計算明細書 | 譲渡所得の計算の根拠 | 必須 |
| 仲介手数料や諸費用の領収書 | 費用控除の証明 | 必須 |
| 固定資産税納付書 | 年間の税額証明 | 推奨 |
| 住民票・本人確認書類 | 申告者の本人確認用 | 必須 |
| 3000万円特別控除の証明書類 | 控除適用時の証明(住民票や居住証明など) | 該当者のみ必須 |
これらの書類が揃っていないと、控除や特例の適用が受けられなくなる場合があるため、早めの準備と確認が重要です。
家売却 確定申告 書類の取得方法 - 書類発行元・申請窓口・オンライン取得の方法と注意点
必要書類の多くは発行元や申請方法が異なります。以下のリストで取得先や注意点を整理します。
・売買契約書・取得時の契約書
不動産会社や仲介業者から受領。紛失時は再発行依頼が可能か確認が必要。
・登記事項証明書(登記簿謄本)
管轄の法務局窓口、もしくは法務省オンラインサービスで取得可能。手数料が発生。
・仲介手数料や諸費用の領収書
各支払い先(不動産会社・司法書士など)から発行。再発行には時間がかかる場合があるため早めに依頼。
・固定資産税納付書
市区町村役場または税務課窓口で確認・再発行可能。必要に応じて取得。
・住民票・本人確認書類
住民票は市区町村役場、本人確認書類は運転免許証やマイナンバーカード等を準備。
・3000万円控除の証明書類
居住用財産の特例を受ける場合、住民票や実際の居住を証明する書類が必要。役所で取得。
ポイント
オンライン取得が可能な書類も増えていますが、発行までに日数を要する場合があるため、余裕を持って申請しましょう。
家売却 確定申告 書類の保管期間と紛失時の対応策 - 保存義務期間と紛失時の再発行手順
確定申告で使用した書類は、税務調査などに備え最低5年間の保管が推奨されています。特に譲渡所得や控除を伴う場合は、保存期間中に税務署から問い合わせがあることも。
保管期間の目安
- 申告書控えや添付書類:5年間
- 取得時・売却時の契約書:7年間保管が望ましい
紛失時の対応策
- 売買契約書や領収書:不動産会社など発行元へ再発行依頼
- 登記事項証明書:法務局で再取得
- 住民票・固定資産税納付書:各自治体窓口で再発行可能
注意点 再発行には日数や手数料がかかるため、紛失を避けるためにも原本とコピーを分けて保管し、必要書類の有無を毎年確認すると安心です。
家売却の確定申告手続きの流れと書き方ガイド
家を売却した際の確定申告は、正しい手続きと書類の準備が重要です。売却益が出た場合だけでなく、損失が出た場合や控除を活用したい場合も申告が必要です。まずは申告が必要か不要かを確認し、必要な場合は確定申告の手順を押さえておきましょう。
強調すべきポイントは以下の通りです。
- 売却益が出た場合や特例を使う場合は確定申告が必要
- 売却した翌年の2月16日から3月15日が申告期間
- 必要書類を事前にチェックし、抜け漏れなく準備
下記の表は、確定申告に必要な主な書類と入手先、ポイントをまとめたものです。
| 書類名 | 入手先 | 注意点・ポイント |
|---|---|---|
| 売買契約書 | 売主・買主 | 売却額や日付、手数料の記載を確認 |
| 登記事項証明書 | 法務局 | 最新の内容を取得 |
| 取得費の証明書(領収書等) | 不動産会社等 | 取得費用の内訳を把握 |
| 譲渡所得計算明細書 | 税務署・国税庁 | 正確な金額を記載 |
| 確定申告書B・第三表 | 税務署・国税庁 | 譲渡所得を記載する専用欄を利用 |
家売却 確定申告 書き方の基本 - 譲渡所得内訳書など主要申告書類の記入要点
確定申告を行う際は、譲渡所得の計算と各種控除の適用がカギとなります。譲渡所得内訳書には、売却価格や取得費、譲渡費用などを正確に記入します。特に3000万円控除や特例を利用する際は、その旨を申告書に明記する必要があります。
記入時の要点をリスト化します。
- 売却価格・取得費・譲渡費用を正確に記載
- 居住用財産の3000万円控除を利用する場合は該当欄にチェック
- 減価償却の計算や損失通算がある場合は計算ミスに注意
- 必要書類を添付して提出すること
申告書には、自宅や土地、マンションなどの種別や所有期間、適用する控除の詳細も記載します。記載内容に不備があると控除が認められない場合もあるため、記入例や国税庁の公式ガイドを参考に慎重に記載してください。
家売却 確定申告 e-tax での申告方法
e-taxを活用した電子申告は、スマートフォンやパソコンから24時間いつでも手続き可能で、書類の提出もオンラインで完結します。マイナンバーカードがあれば、よりスムーズに申告できます。
e-tax利用の主なメリットと手順
- 国税庁のe-taxサイトにアクセス
- 利用者識別番号・マイナンバーカードでログイン
- 「譲渡所得」の入力画面で売却内容を入力
- 必要書類をPDF等で添付
- 内容確認し電子署名を付けて送信
- 控えのデータを必ず保存
e-taxなら郵送や窓口提出の手間が省け、還付金の受け取りも早くなります。初めての方でも画面案内に沿って進めることで、正確な申告が可能です。
家売却 確定申告 手続きの流れ - 申告準備から提出、納税までの一連の流れ
家売却の確定申告は、以下の流れで進みます。
- 売却に関する書類の収集と準備
- 譲渡所得や控除の計算
- 申告書類への記入・必要書類の添付
- e-taxや税務署窓口、郵送での提出
- 税額が発生する場合の納税(原則として3月15日まで)
申告を忘れた場合や遅れた場合は、延滞税やペナルティが科されることがあるため、早めの準備と正確な手続きを心がけましょう。不明点は税務署や専門家に相談するのも有効です。
家売却時に活用できる主な控除・特例制度の徹底解説 - 節税効果が高い制度の詳細と適用条件
家を売却した際の確定申告では、節税につながるさまざまな控除や特例制度を活用できます。特に、居住用財産の特別控除や譲渡損失の繰越控除などは、税負担を大幅に軽減する重要なポイントです。適用条件や申告方法を正しく理解することで、不要な税金を支払うリスクを防ぎ、安心して手続きを進めることが可能です。
家売却 確定申告 3000万円控除の条件 - 居住用財産の特別控除の適用要件と注意点
家売却の際に最も活用されるのが「居住用財産の3000万円特別控除」です。これはマイホームを売却した場合、譲渡所得から最大3000万円まで控除できる制度です。
適用条件は以下の通りです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 売却物件 | 自分が居住していた家屋またはその敷地 |
| 居住期間 | 原則として譲渡した日まで引き続き住んでいたこと(転居後3年以内の売却も対象) |
| 親族・同族会社への売却 | 該当する場合は控除適用不可 |
| 他の特例との併用 | 一定の制限あり |
注意点
- 控除を受ける場合でも確定申告は必須です。
- 過去に同一特例を利用している場合、再度の適用には制限があります。
家売却 確定申告 減価償却や取得費加算
譲渡所得の計算では、売却した家の取得費や減価償却費の扱いが重要です。取得費には購入代金だけでなく、仲介手数料や登記費用も含まれます。建物の場合は減価償却を考慮して計算し、売却時の取得費から償却済み分を差し引きます。
減価償却費の計算方法例
- 建物購入価格×0.9(消費税等を除く場合)
- 上記金額÷法定耐用年数×所有年数
取得費加算の主な内容
- 売却時の仲介手数料
- 登記費用
- 改修・リフォーム費用(条件あり)
これらを正しく計算することで、譲渡所得を圧縮し税額を抑えることができます。
家売却 確定申告 譲渡損失の繰越控除 - 損失発生時に使える控除制度の内容と申告時のポイント
家売却で譲渡損失が発生した場合、「譲渡損失の繰越控除」を活用できます。この制度では、一定の住宅ローンが残っている場合やマイホーム売却で損失が出た場合に、損失分を他の所得と通算し、3年間にわたり繰り越して所得税・住民税から控除できます。
主な要件
- 売却した家が居住用財産であること
- 売却時点で住宅ローンが残っていること
- 損失額を翌年以降も繰り越すには毎年確定申告が必要
申告時のポイント
- 損失を証明する書類の添付(売買契約書、ローン残高証明書など)
- 損益通算の正確な計算
損失が大きい場合でも適切に申告すれば、将来の税負担を減らすことができます。
家売却後にかかる税金の種類と計算方法をやさしく解説
家を売却した際には、主に譲渡所得税と住民税が発生します。これらは売却益、つまり購入価格や諸費用、減価償却を差し引いた利益に対して課税されます。売却時には、「3000万円控除」などの特例が適用できることもあり、課税対象額が大きく変わる場合があります。税金の仕組みや計算方法を正しく理解し、余裕を持って準備することが重要です。
家売却 確定申告 税金計算の基礎 - 譲渡所得税・復興特別所得税・住民税の計算式
家売却に伴う税金は、「譲渡所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つが基本となります。税額の計算は以下の流れで行います。
1.譲渡所得の算出
・譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
2.課税譲渡所得の計算
・控除(3000万円控除など)を差し引く
3.税率の適用
・期間5年超(長期)か5年以下(短期)によって税率が異なる
主な税率は以下のとおりです。
| 区分 | 譲渡所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 長期 | 15% | 0.315% | 5% |
| 短期 | 30% | 0.63% | 9% |
※長期所有は5年超、短期所有は5年以下です。
家売却 確定申告 計算シミュレーション - 具体的な事例を用いたシミュレーショ
例えば、購入価格2,000万円で10年前に取得し、売却価格3,000万円、諸費用200万円、3000万円特別控除が適用できる場合を考えます。
- 譲渡所得=3,000万円-(2,000万円+200万円)=800万円
- 課税譲渡所得=800万円-3,000万円=0円
このケースでは課税額が0円となり、税金がかかりません。
もし控除が適用できない場合は、課税譲渡所得に上記の税率が適用されます。
控除や特例の有無で納税額が大きく変わるため、条件をよく確認しましょう。
家売却 確定申告 税率と税額早見表 - 売却益別の税率とおおよその納税額を一覧化
売却益ごとの税率と納税額の目安をまとめます。
| 売却益 | 長期譲渡所得税・復興税・住民税合計 | 短期譲渡所得税・復興税・住民税合計 |
|---|---|---|
| 100万円 | 約20.315万円 | 約39.63万円 |
| 500万円 | 約101.575万円 | 約198.15万円 |
| 1,000万円 | 約203.15万円 | 約396.3万円 |
*控除や特例適用前の目安です。実際の納税額は各種控除や取得費用等で変動します。
*5年超の長期所有なら税率が低くなるため、売却タイミングも重要です。
*納税は原則翌年の確定申告時に一括で行うため、事前の資金準備も欠かせません。
家売却でよくあるトラブル・注意点と対処法
家を売却した際の確定申告には、申告漏れや誤った書類記載、費用計上ミスなど、さまざまなトラブルが発生することがあります。これらを防ぐためには、事前準備と正確な知識が不可欠です。特に、3000万円控除や減価償却費の計算、必要書類の準備などは専門的な知識が求められます。不動産売却での確定申告が不要なケースもありますが、条件を正しく把握しておかないと予期せぬ課税やペナルティを受けるリスクも。売却後の税金や申告の流れを事前に確認し、万全の体制で臨むことが重要です。
家売却 確定申告 忘れた場合の対処法 - 期限後申告・修正申告の具体的な対応策と流れ
確定申告を忘れた場合でも、できるだけ早く対応することでトラブルを最小限に抑えられます。期限後申告や修正申告の際は、下記の流れで進めましょう。
| 手順 | ポイント |
|---|---|
| 1. 必要書類の再確認 | 売買契約書・登記事項証明書・譲渡所得の計算書などを用意 |
| 2. 期限後申告書作成 | 国税庁サイトやe-taxを利用して申告書を作成 |
| 3. 税務署への提出 | 持参・郵送・e-taxのいずれかで速やかに提出 |
| 4. 納税 | 必要に応じて延滞税や加算税が発生する点に注意 |
申告を怠ると延滞税や無申告加算税が課されるため、速やかな対応が不可欠です。
家売却 確定申告 減価償却や費用計上ミスの防止
減価償却や諸経費の計上は、譲渡所得額の算出に直結します。下記のようなミスを防ぐことが大切です。
- 減価償却費の計算間違い
- 仲介手数料やリフォーム費用の漏れ
- 取得費や譲渡費用の証明資料の紛失
主なミス防止ポイント
- 取得時の契約書や領収書を必ず保管
- 減価償却の計算式を国税庁のシミュレーターで確認
- 3000万円控除や特例の適用条件を再確認
これらを意識しておくことで、申告内容の正確性が高まり、税務署からの指摘リスクも低減します。
家売却 確定申告 税務署からの問い合わせ対応 - 税務署質問への準備方法と回答のポイント
税務署から問い合わせが来る場合、申告内容に不明点や誤りが疑われているケースが多いです。冷静に下記ポイントを押さえて対応しましょう。
| 問い合わせで多い内容 | 準備・対応のコツ |
|---|---|
| 取得費や譲渡費用の証拠 | 契約書・領収書・明細書を整理しておく |
| 減価償却計算の根拠 | 建物の取得年月日・面積・用途を明確に説明 |
| 控除や特例の適用理由 | 住民票や居住実績を証明できる書類を準備 |
正確な書類と根拠をもとに説明することで、スムーズな解決につながります。事前準備を徹底し、指摘事項には迅速かつ丁寧に対応することが信頼性を高めるポイントです。
家売却後の確定申告に関するQ&A・よくある質問まとめ
家を売ったら確定申告は必要ですか?
家を売却した場合、原則として確定申告が必要です。売却によって発生した譲渡所得の有無にかかわらず、税務署への申告が義務付けられています。ただし、売却による利益が発生しない場合や損失が出た場合でも、特例や控除の適用を受けるには確定申告を行う必要があります。以下のケースでは申告が不要となることもあります。
- 相続財産の売却で損失のみ発生した場合
- 収入金額が譲渡所得控除適用後にゼロとなる場合
迷った場合は、税務署や専門家に相談するのがおすすめです。
家を1000万円で売ったら税金はいくらかかりますか?
家を1000万円で売却した際の税額は、取得費や譲渡費用、控除額によって大きく異なります。納税額の目安をシミュレーションするには以下の要素が重要です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 1,000万円 |
| 取得費 | 購入時の価格+登録免許税などの諸費用 |
| 譲渡費用 | 仲介手数料や印紙税など |
| 3000万円控除 | マイホーム売却の場合に適用可能 |
| 課税譲渡所得 | 売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除 |
例: 取得費と譲渡費用の合計が800万円、3000万円控除が適用できれば課税譲渡所得は0となり、税金はかかりません。詳細な計算は専門家やシミュレーションツールで確認しましょう。
確定申告を自分でする場合のポイント
初めて自分で家売却の確定申告を行う方は、以下のポイントを押さえるとスムーズです。
- 必要書類(売買契約書、登記事項証明書、取得費や譲渡費用の領収書など)を事前に整理
- 「譲渡所得の内訳書」「確定申告書B」など税務署指定の書類を正確に記載
- e-taxを利用すれば自宅からオンライン申告が可能
- 申告書の作成方法は国税庁のサイトや申告書作成コーナーを活用
提出期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、必ず期限内に済ませてください。
3000万円控除と併用できる節税策
自宅売却時の3,000万円特別控除は非常に大きな節税メリットがあります。さらに、以下の特例と併用可能かがよく問われます。
| 節税策 | 3,000万円控除との併用可否 |
|---|---|
| 居住用財産の買換え特例 | 不可 |
| 譲渡損失の損益通算・繰越控除 | 可(但し条件あり) |
| 配偶者控除など | 可 |
特例の併用可否や適用条件は複雑なため、必ず国税庁や税理士に確認しましょう。
家売却後の確定申告でよくあるミス
家売却後の確定申告で多いミスを知っておくことで、トラブルを未然に防げます。
- 取得費や譲渡費用の計算もれや領収書紛失
- 3000万円控除の適用条件を満たしていない
- 申告期限を過ぎてしまう
- e-tax利用時の添付書類の不備
- 譲渡所得税の納税忘れ
これらを防ぐためには、事前準備と書類の再確認が重要です。分からない点は税務署や専門家に相談しながら進めましょう。
家売却の確定申告を成功させるためのプロのアドバイスと最新情報
家を売却した際には、確定申告が必要なケースが多く見受けられます。特に、譲渡所得が発生する場合や3000万円特別控除を利用する場合は、必ず申告が求められます。申告が不要なケースもありますが、判断には注意が必要です。例えば、相続した不動産やマイホームの売却時にも条件によっては申告が必要となります。確定申告を怠ると追徴課税のリスクがあるため、必要書類の準備や時期の把握は重要です。
主な必要書類には、売買契約書、登記事項証明書、譲渡所得の計算書、取得費用の証明資料などが含まれます。適切な控除や特例を活用することで、税金負担を大きく減らせる可能性があります。特に、3000万円控除は自宅売却時に有効なため、確実な申告手順を押さえておきましょう。
家売却 確定申告を税理士に依頼する場合のポイント - 費用の相場や良い税理士の選び方のポイント
税理士に申告業務を依頼する場合、費用相場は5万円〜15万円ほどが一般的です。物件の規模や申告内容の複雑さによって変動します。専門家に依頼するメリットは、控除や特例の見落とし防止、書類作成の正確性、e-Taxなどの電子申告対応など、安心感と効率の高さです。
良い税理士を選ぶポイントは以下の通りです。
- 不動産売却の確定申告に実績がある
- 複雑な控除や特例の適用経験が豊富
- 費用が明瞭で追加料金が発生しない
- 丁寧なヒアリングや説明がある
税理士選びは、失敗や申告漏れを防ぐためにも慎重に行いましょう。無料相談や見積もりを活用して、納得できる専門家を探すことが大切です。
家売却 確定申告の最新法改正・トピック
令和6年(2024年)には、定額減税制度の導入や一部の控除条件の変更など、税制改正が行われています。特に注目すべきは、定額減税の適用方法や、譲渡所得に関する控除の新ルールです。これにより、対象となる場合は申告時に新たな記載欄への記入が必要となります。
また、e-Taxによるオンライン申告がより推奨されており、添付書類の電子提出やマイナンバー活用の簡素化が進んでいます。申告時期も例年通り2月中旬から3月中旬ですが、土日祝日の関係で最終日は変動することもあるため、国税庁の最新情報を確認しましょう。
主な改正ポイント
| 内容 | 令和6年の改正点 |
|---|---|
| 定額減税 | 所定の所得要件を満たす場合、定額減税が適用される |
| 申告書の記載 | 新たな項目・記載欄への入力が必要 |
| e-Tax申告 | 添付書類の電子化やマイナンバーの利便性向上 |
家売却 確定申告 実際の体験談・口コミ - 成功例と失敗例から学ぶ確定申告の実践的ポイント
実際に家を売却した方々の体験談では、早めの書類準備や税理士への相談が成功の秘訣として挙げられています。以下はよくある成功例と失敗例です。
成功例
- 必要書類をリスト化し、売却時から保管しておいた
- 3000万円控除を正しく適用でき、税額が大幅に軽減された
- e-Taxを利用し、スムーズに申告を完了できた
失敗例
- 必要書類の紛失で申告が遅れた
- 控除条件を勘違いし、控除を受け損ねた
- 期限までに申告できず、延滞税が発生した
体験者の声からも、準備と確認の徹底がトラブル防止のカギであることがわかります。不明点は国税庁サイトや税理士に早めに相談することが、安心して申告を終えるポイントです。
まとめ
家を売却したら、確定申告が必要かどうかを必ず確認しましょう。
なぜなら、申告の要否を正しく判断し、必要な手続きを怠らなければ、節税につながる特例を活用でき、追徴課税などのリスクも回避できるからです。
たとえば、3,000万円特別控除や譲渡損失の繰越控除を利用すれば、課税額をゼロまたは大幅に軽減できるケースが少なくありません。一方で、申告を忘れると無申告加算税や延滞税が発生する恐れがあります。
不動産の売却後は、必ず確定申告の必要性を確認し、正しい知識と書類をもって期限内に申告を行いましょう。
会社概要
会社名・・・株式会社MINAMI
所在地・・・〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号・・・0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------
ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------