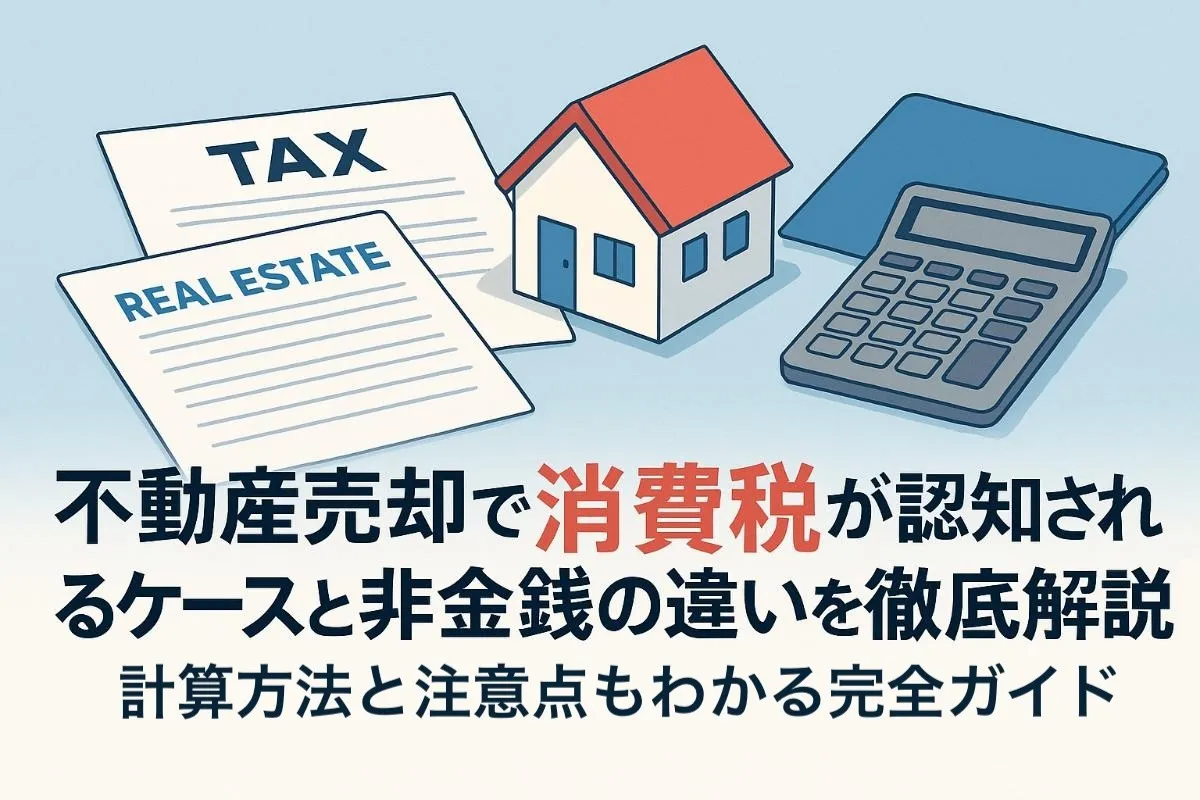不動産売却で消費税が認知されるケースと非金銭の違いを徹底解説!計算方法と注意点もわかる完全ガイド
2025/11/09
不動産を売却する際、“消費税がかかるのは建物だけ”と聞いたことはありませんか?実は、売却する物件の種類や売主の立場(個人・法人・個人事業主)、取引内容によって消費税の取り扱いは大きく異なります。例えば、2023年度の統計では、事業用建物の売却における消費税課税事例が年間8万件以上と発表されている一方、土地取引の大半は非課税です。
「想定外の課税や申告ミスで、数百万円単位の追加費用が発生したら…」と不安を感じていませんか?正しい知識なしでは、余計な納税や損失を招くリスクも。
本記事を読み進めるだけで、あなたに必要な「損をしない売却の知識」が手に入ります。
目次
不動産売却における消費税の全体像と基礎知識
不動産売却における消費税の基本ルール
不動産売却において消費税が発生するかどうかは、取引の性質や売主の立場によって異なります。国内取引で、かつ事業としての取引(課税事業者によるもの)が前提となり、個人間の取引や非事業者が売主の場合、原則として消費税は課税されません。売却代金に消費税が含まれるかを判断する際は、以下の三つの条件を満たす必要があります。
- 取引が国内で行われていること
- 事業として行う資産の譲渡であること
- 対価を伴う取引であること
特に不動産会社や法人が売主となる場合には、消費税の課税対象となるケースが多くなります。
土地と建物の消費税の違いと課税区分の根拠
不動産売却では、土地と建物で消費税の扱いが異なります。土地は「消費税法」により非課税とされており、売買価格に消費税は課されません。一方、建物は課税対象となり、売主が課税事業者であれば売却時に消費税が発生します。これにより、建物部分の価格にのみ消費税が加算されるのが一般的です。
下記のテーブルで区分を整理します。
| 区分 | 課税対象 | 消費税発生の有無 |
| 土地 | 非課税 | なし |
| 建物 | 課税 | あり |
中古物件や住宅の場合でも、建物部分のみが消費税の計算対象となります。土地と建物の価格が明確に区分されていないときは、按分計算が必要です。
個人・法人・個人事業主別の消費税適用の違い
不動産売却時の消費税の適用は、売主が個人、法人、個人事業主のいずれかによって大きく異なります。
- 個人の場合
居住用不動産を売却する個人は、通常消費税の課税対象外です。ただし、事業用不動産や個人事業主として売却する場合には課税事業者であれば消費税が発生します。 - 法人の場合
法人が不動産を売却するときは、事業取引に該当し建物部分に消費税が課されます。申告や納税義務が生じ、簡易課税制度の利用が可能な場合もあります。 - 個人事業主の場合
年間売上が1,000万円を超える課税事業者は、事業資産売却時に消費税の申告が必要です。免税事業者であれば課税されませんが、インボイス制度の影響も考慮が必要です。
一覧表で違いをまとめます。
| 売主区分 | 課税対象の範囲 | 消費税申告義務 | 特徴 |
| 個人 | 原則非課税 | なし | 居住用は非課税、事業用は条件により課税 |
| 法人 | 建物部分が課税対象 | あり | 申告・納税が必要、簡易課税も選択可 |
| 個人事業主 | 事業用資産が対象 | 売上に応じて | 売上1,000万円超で課税事業者 |
このように、売主の立場によって消費税の取り扱いが大きく異なるため、自身の状況に合わせた正しい知識が不可欠です。予期せぬ税負担を避けるためにも、専門家への相談や確認をおすすめします。
不動産売却で消費税が課税されるケースと非課税ケースの詳解
課税対象となる不動産売却の具体例
不動産売却における消費税は、全ての取引に課税されるわけではありません。課税対象となるのは、主に事業用建物や投資用不動産の売却時です。個人が自宅を売却する場合と異なり、事業者や法人が事業の一環として建物を売却する際に消費税が発生します。
下記のようなケースが課税対象です。
- 法人や個人事業主が保有する建物やマンションなどを売却した場合
- 事業用不動産を課税事業者が売却した場合
- 投資用物件の売却で課税売上高が1,000万円を超える場合
また、土地部分は非課税ですが、建物部分には消費税がかかります。消費税の計算方法は「建物価格×税率(通常10%)」で算出されます。売主が課税事業者かどうかで発生の有無が決まるため、事前確認が重要です。
非課税となる売却事例とその根拠
不動産売却でも消費税が発生しない、つまり非課税となる事例もあります。代表的なのは個人が居住用目的で所有していた住宅や、土地の売却です。国税庁の規定により、土地自体の譲渡には消費税が課されません。
非課税となる具体的な例は以下の通りです。
- 個人が自宅として使用していた住宅の売却
- 土地のみの売却(建物がない場合)
- 非居住者が所有する不動産の売却で国内での課税要件を満たさない場合
土地と建物を一括売却する場合、建物部分の価格と土地部分の価格を按分して計算します。住宅ローンの完済や売却益の発生有無にかかわらず、非課税ルールが適用されます。
免税事業者・簡易課税事業者の区別と影響
不動産売却における消費税の納付義務は、売主が「課税事業者」か「免税事業者」かで変わります。課税事業者とは、前々年の課税売上高が1,000万円を超える法人や個人事業主のことです。一方、1,000万円以下の場合は免税事業者となり、消費税の納付義務はありませんが、売買時の扱いは注意が必要です。
また、「簡易課税事業者」は、事業区分ごとにみなし仕入率を使って簡便に消費税額を計算できる制度です。不動産業の場合、みなし仕入率は40%となり、消費税還付や納付額に影響します。
| 区分 | 消費税納付義務 | 売却時の対応 |
| 課税事業者 | あり | 建物部分に消費税が発生 |
| 免税事業者 | なし | 原則消費税の請求不可 |
| 簡易課税事業者 | あり | みなし仕入率で計算 |
売主の区分によって、仕訳や消費税申告の方法も異なるため、事前に制度を確認し適切な納付や処理を行うことが重要です。事業用・投資用の不動産取引では特に慎重な対応が求められます。
消費税の計算方法・按分計算・仕訳例を徹底解説
消費税計算の基本式と実際の計算例
不動産売却時の消費税は、建物部分に対してのみ課税され、土地部分は非課税となります。消費税の基本的な計算式は「建物価格×消費税率」で求められます。例えば、建物の売却価格が2,000万円、消費税率が10%の場合、計算式は2,000万円×0.1=200万円となり、200万円が消費税額です。
消費税の課税対象となるのは、課税事業者や法人が事業用として売却する場合です。個人が居住用の住宅を売却するケースでは、消費税は発生しません。売主が課税事業者かどうかは、消費税申告義務の有無や取引形態によって異なります。
| 項目 | 消費税がかかる場合 | 消費税がかからない場合 |
| 売主 | 法人・課税事業者 | 個人(居住用)・免税事業者 |
| 資産 | 建物 | 土地 |
| 用途 | 事業用・投資用 | 自宅用・非事業用 |
土地建物按分計算の実務的ポイント
土地と建物が一体で売却される場合、消費税の計算は必ず建物と土地で分けて算出します。建物価格と土地価格の按分には、一般的に「固定資産税評価額」を用います。これは市区町村から発行される固定資産税通知書に記載されています。
按分計算の手順は以下の通りです。
- 固定資産税評価額で建物と土地の割合を算出
- 売却総額にそれぞれの割合を掛けて按分
- 建物部分に対してのみ消費税を計算
注意点として、実勢価格と評価額が大きく乖離している場合は、専門家に相談することが重要です。また、税務調査時には按分根拠資料の保存が求められるため、証拠書類は必ず保管してください。
仕訳と会計処理の実践例
仕訳例は取引主体によって異なります。下記は主なケースです。
【個人事業主の場合】
- 建物売却時:
売掛金(売却額)/建物(取得原価)、課税売上消費税/仮受消費税
【法人の場合】
- 売却仕訳:
現金または売掛金(売却額)/建物(帳簿価額)、仮受消費税
【免税事業者の場合】
- 消費税の計上は不要ですが、帳簿には取引内容を明記
取引主体 仕訳項目 ポイント 個人 帳簿外処理 売買契約書の保管必須 個人事業主 課税売上、仮受消費税 消費税申告が必要な場合あり 法人 仮受消費税の計上 消費税申告・納付が必須 会計処理では、消費税の納付時期や申告手続きも重要です。特に課税事業者や簡易課税制度を利用する場合は、消費税申告書の正確な作成が求められます。按分や仕訳に迷う場合は税理士への早めの相談が有効です。
不動産売却に伴うその他の税金・費用との違いと関係性
不動産売却では、消費税以外にもさまざまな税金・費用が発生します。主なものは譲渡所得税、印紙税、仲介手数料などです。これらはそれぞれ発生タイミングや課税対象が異なり、正しく理解することが重要です。
譲渡所得税・印紙税・仲介手数料の概要と消費税との違い
不動産売却時に関係する主な税金・費用は以下の通りです。
| 税金・費用 | 特徴 | 発生タイミング | 消費税との違い |
| 譲渡所得税 | 売却益に対して課税される | 売却後、確定申告で納付 | 取引自体に消費税はかからない |
| 印紙税 | 売買契約書に貼る | 契約締結時 | 取引額に応じて課税、消費税とは別途 |
| 仲介手数料 | 不動産会社へ支払う手数料 | 売買成立時 | 手数料自体に消費税が課される |
- 譲渡所得税は、売却益が出た場合のみ発生し、確定申告が必要です。
- 印紙税は、契約書作成時に必須ですが、消費税とは直接関係しません。
- 仲介手数料は、不動産会社のサービス対価であり、消費税の課税対象となります。
消費税がかかる費用と非課税費用の具体例
不動産売却時には、課税対象と非課税対象となる費用が明確に分かれています。以下に主な例を示します。
| 費用項目 | 消費税の有無 | 備考 |
| 建物の売却代金 | かかる(課税) | 個人の場合は原則非課税だが、課税事業者の場合に課税 |
| 土地の売却代金 | かからない(非課税) | 土地は非課税資産 |
| 仲介手数料 | かかる(課税) | 不動産会社への支払い |
| 司法書士報酬 | かかる(課税) | 登記や手続費用 |
| ローン関連手数料 | かかる(課税) | 繰上返済・事務手数料など |
| 印紙税 | かからない(非課税) | 国税であり消費税対象外 |
- 建物の売却代金は、法人や課税事業者が売主の場合に消費税が発生します。
- 土地の売却代金や印紙税は非課税です。
- 司法書士報酬や仲介手数料などは消費税が含まれるため、支払い総額に注意しましょう。
不動産売却時の費用総額シミュレーション例
実際に不動産を売却した場合の費用総額をシミュレーションすることで、資金計画が立てやすくなります。以下は、建物と土地の売却、各種手数料を含めた費用内訳の例です。
| 項目 | 金額(例) | 消費税 | 支払いタイミング |
| 建物売却代金 | 2,000万円 | 200万円(10%) | 売却時 |
| 土地売却代金 | 1,000万円 | 0円 | 売却時 |
| 仲介手数料 | 99万円 | 9.9万円 | 売買成立時 |
| 司法書士報酬 | 10万円 | 1万円 | 引渡時 |
| ローン関連手数料 | 5万円 | 0.5万円 | ローン返済時 |
| 印紙税 | 3万円 | 0円 | 契約締結時 |
- 合計費用(消費税含む)を把握することで、受け取れる金額や納税額を正確に見積もることができます。
- 各費用の消費税の有無に注意し、事前に不動産会社や専門家に相談することがリスク回避につながります。
不動産売却に関する税金や費用の仕組みを理解し、適切な準備を進めることで、トラブルや予期せぬ出費を防ぐことができます。
法人・個人事業主・免税事業者の特殊論点と最新実務対応
法人・個人事業主の消費税申告フローと注意点
法人や個人事業主が不動産を売却する際、消費税申告は厳格なフローに従う必要があります。まず、事業用資産として売却する場合、消費税課税事業者であれば納税義務が発生します。売却時の仕訳では、建物部分の譲渡に対して消費税額を明確に計上することが重要です。消費税の申告書作成時には、売上の内訳や消費税区分ごとに正確な金額を記載し、課税売上割合による按分計算も求められるケースがあります。また、建物と土地で税区分が異なるため、按分計算による課税区分の明確化が必須です。
下記の表は、不動産売却時に法人・個人事業主が押さえるべき申告フローの要点をまとめています。
| 項目 | 内容 |
| 売却資産の区分 | 土地は非課税、建物は課税対象 |
| 消費税課税事業者の確認 | 年間売上等で判定 |
| 仕訳作成 | 建物譲渡益と消費税額の計上 |
| 申告書作成 | 按分計算・区分記載の徹底 |
| 納付 | 原則として翌期以降納付 |
- 消費税還付や簡易課税制度の適用可否も事前に確認しましょう。
免税事業者の売却時の消費税対応とインボイス制度
免税事業者が不動産を売却する場合、原則として消費税の納税義務はありません。しかし、インボイス制度(適格請求書等保存方式)が導入されたことで、買主が法人・課税事業者である場合、インボイスを発行できない免税事業者との取引は仕入税額控除が制限されるようになりました。これにより、売却価格や取引条件に影響を及ぼすことが増えています。
免税事業者が今後も不動産取引を継続する場合は、課税事業者への転換やインボイス発行事業者登録の検討が必須です。特に、売却時に「インボイスが必要か」「今後の売却計画にどう影響するか」を早めに確認しておくことが重要です。
- インボイスが発行できないと、買主が仕入税額控除を受けられなくなる
- 売却価格に影響するケースが増加
- 課税事業者転換のタイミングに注意
事業用資産や投資用不動産売却の消費税の特殊性
事業用資産や投資用不動産を売却する際には、消費税の課税関係が複雑になります。土地部分は非課税ですが、建物部分は課税対象となるため、売却価格の按分計算が必要です。特に、事業用不動産や投資用マンションの売却では、課税売上割合による消費税額の調整や、簡易課税制度の適用の有無が重要な論点となります。
節税の観点からは、消費税還付の可否や仕入税額控除の適用範囲をしっかり把握することが不可欠です。さらに、法人・個人を問わず、譲渡資産の取得時期や用途、譲渡益の仕訳方法など、実務上の細かな対応が求められます。
| 物件タイプ | 土地 | 建物 | 消費税課税条件 |
| 事業用不動産 | 非課税 | 課税 | 課税事業者のみ納税義務 |
| 投資用不動産 | 非課税 | 課税 | 按分計算必須 |
| 居住用 | 非課税 | 非課税/課税 | 個人用途は非課税が多い |
- 建物部分の価格按分や用途区分を正確に記載することが、税務調査でも重要視されます
- 節税策や最新の制度変更にも常に目を配りましょう
消費税申告・納税の具体的なフローと注意点
消費税申告から納付までの基本的な流れ
不動産売却で発生した消費税の申告と納付には、正確な知識が不可欠です。売却物件が課税対象であれば、個人・法人ともに消費税の申告義務が生じます。申告期限は通常、事業年度終了日の翌日から2か月以内です。納付も同じく2か月以内となり、期限を過ぎるとペナルティが発生するため注意が必要です。
下記は申告・納付に必要な主な書類です。
| 書類名 | 内容 |
| 消費税確定申告書 | 消費税の申告に必須の書類 |
| 売上・仕入明細書 | 取引ごとの消費税計算に必要 |
| 領収書・請求書 | 売却時・経費証明用 |
| 按分計算書 | 土地と建物の消費税按分記録 |
物件の種類や売主の事業形態(個人事業主、法人、免税事業者など)によって手続きが異なるため、正確な判定が求められます。
申告ミス・納付遅延時のペナルティと対処法
消費税の申告や納付が遅れた場合、いくつかのペナルティが課されます。代表的なものは遅延税と過少申告加算税です。
- 遅延税:納付が遅れた日数に応じて加算され、支払額が増えます。
- 過少申告加算税:申告内容が正しくない場合、追徴課税として課されます。
ペナルティを回避するためには、期限前の準備と正確な計算が不可欠です。もしミスや遅延が発生した場合は、速やかに税務署へ相談し、必要な修正申告や納付手続きを進めましょう。法人・個人問わず、早期対応が負担軽減につながります。
適切な帳簿保存と証憑管理の実務ポイント
消費税申告においては、帳簿と証憑(証拠書類)の適切な管理が求められます。記帳方法としては、売上や経費ごとに消費税区分を明確に記載し、按分計算や課税対象の判定が容易になるよう整理することが重要です。
- 帳簿のポイント
- 取引ごとに消費税額を明記
- 土地・建物の按分計算を記載
- 課税・非課税の区分を明確化
- 証憑管理のポイント
- 領収書、請求書、契約書は原本で保存
- 電子帳簿保存法に則った管理も有効
- 7年間の保存義務を遵守
帳簿や証憑が整っていれば、税務調査の際や仕訳作業、消費税申告の精度が大きく向上します。不安がある場合は専門家へ相談し、最新の税制に合わせた管理体制を構築しましょう。
不動産売却時の消費税対策・節税テクニック
消費税還付の条件と活用方法
不動産売却で消費税還付を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、売主自身が消費税の課税事業者であることが前提となります。例えば、法人や個人事業主で一定の売上高を超える場合に該当します。還付の対象となるのは、主に事業用不動産の売却で、居住用の不動産売却では消費税は非課税のため対象外です。
還付を受ける際は、消費税申告を正確に行い、仕訳や按分計算が正しいことが重要です。特に建物と土地の按分計算や、簡易課税制度の適用有無に注意しましょう。
| 還付対象 | 具体例 | ポイント |
| 課税事業者の事業用不動産 | オフィス・店舗など | 消費税申告と仕訳の正確さが必要 |
| 簡易課税適用事業者 | 小規模法人・個人事業主 | 按分計算の方法に注意 |
| 居住用不動産 | マンション・戸建て | 非課税のため還付対象外 |
還付申告の手続きは期限があるため、早めの準備が欠かせません。
売却タイミングによる税負担軽減策
不動産売却時の消費税額は、売却タイミングによって変動します。特に消費税率改正前後や、自身の課税事業者区分の変更タイミングがポイントです。税率改正前に売却手続きを進めることで、低い税率を適用できるケースがあります。
また、年度内の売上高が基準を超えると課税事業者になるため、売却時期を調整することで課税対象外とできる場合もあります。下記のリストは、タイミング調整による節税ポイントです。
- 売却前後の消費税率を必ず確認
- 課税事業者・免税事業者の判定時期を把握
- 年度内の売上見込みを計算し、課税区分の変更タイミングを検討
- 税率引き上げ前に契約を締結することで負担を軽減
これらの対策は、法人・個人問わず有効です。
税理士・専門家活用のポイント
不動産売却における消費税の計算や還付、仕訳などは非常に複雑です。専門家に依頼することで、税負担の最適化とリスク回避が可能になります。依頼時のチェックポイントを以下にまとめます。
| チェック項目 | 内容 |
| 不動産売却時の消費税経験 | 法人・個人双方の実績があるか確認 |
| 申告・仕訳のサポート範囲 | 消費税申告・還付申請・按分計算の対応可否 |
| 費用の明確化 | 着手金・成功報酬・追加費用の有無を事前確認 |
| 節税提案力 | タイミング調整や簡易課税など多角的なアドバイス |
専門家に相談することで、不安や手間を大幅に軽減できるだけでなく、最適な節税効果が期待できます。信頼できる税理士やコンサルタントを選ぶことが、成功のポイントとなります。
実例で学ぶ不動産売却の消費税Q&Aとトラブル回避策
個人の自宅売却時に消費税がかからない理由
個人が所有する自宅を売却する場合、消費税は原則として課税されません。これは、住宅用の建物や土地の譲渡は「消費税法」で非課税取引に該当するためです。たとえばマイホームやマンションを個人が売却した場合、買主が支払うのは物件価格のみとなり、消費税の上乗せは不要です。
【非課税となる主な理由】
- 個人が事業として不動産売却を行っていない場合
- 居住用建物や土地の譲渡は消費税法で非課税とされている
もしも個人事業主が事業用資産として保有していた不動産を売却する場合、課税対象になるケースもあるため、用途や所有形態による違いに注意が必要です。
法人の事業用不動産売却における課税実務
法人が保有する事業用不動産を売却した場合、建物部分には消費税が課税されます。土地部分は非課税ですが、建物は課税取引となるため、売却額から消費税額を正確に計算する必要があります。
【法人の不動産売却時のポイント】
- 建物部分にのみ消費税が課せられる
- 売却時には消費税申告が必要
- 売却価格の内訳を明確に分けて記載することが重要
実際の申告では、譲渡資産の種類ごとに仕訳を行い、課税売上割合や簡易課税制度の適用可否を確認する必要があります。課税事業者の場合、消費税還付や納付のタイミングも押さえましょう。
| 売主 | 売却対象 | 消費税の扱い |
| 法人 | 建物 | 課税対象 |
| 法人 | 土地 | 非課税 |
土地と建物を同時売却した場合の消費税按分計算
土地と建物をセットで売却する際は、売買契約書でそれぞれの価格を明確に区分することが必要です。建物のみ消費税がかかるため、按分計算が重要となります。
【消費税按分計算の流れ】
- 売買契約書に土地と建物の価格を明記
- 建物価格にのみ消費税を加算
- 按分が不明確な場合、税務署の指摘リスクがある
例えば、総額2,000万円のうち、建物1,000万円・土地1,000万円とした場合、建物1,000万円にのみ消費税が課税されます。按分が曖昧だとトラブルの原因となるので、必ず証拠資料を残すことがトラブル防止のポイントです。
免税事業者や非居住者の特殊ケース
免税事業者や非居住者が不動産を売却する場合、消費税の取扱いが複雑になります。免税事業者は一定の基準期間の売上高が1,000万円以下の場合、消費税の納税義務が免除されますが、インボイス制度導入以降は取引先との契約に影響が出る場合があるため注意が必要です。
非居住者が日本国内の不動産を売却する際は、消費税や所得税の源泉徴収制度など独自のルールが適用されます。
| ケース | ポイント |
| 免税事業者 | 消費税納税義務なし、インボイス発行不可 |
| 非居住者 | 源泉徴収義務や特例申告が必要、事前の確認が不可欠 |
これらの特殊ケースでは、事前に専門家へ相談し、最新の法令や申告方法を確認することがトラブル防止に役立ちます。
2025年以降の最新の法改正・インボイス制度と今後の展望
インボイス制度の概要と不動産売却への影響
2023年10月に導入されたインボイス制度(適格請求書等保存方式)は、不動産売却にも大きな影響を及ぼしています。インボイスの発行が求められるのは消費税課税事業者であり、特に法人や個人事業主が事業用不動産を売却する場合、買主が仕入税額控除を受けるためにはインボイスの発行が必須となります。これにより、免税事業者が売主の場合、買主が仕入税額控除を受けられないため、売却価格に影響が出るケースが増加しています。
インボイス制度対応のために確認すべき主なポイントは以下の通りです。
- 売主が課税事業者か免税事業者か
- インボイス発行の可否
- 不動産売買契約書の記載内容
- 消費税計算・申告の手続き
項目 課税事業者 免税事業者 インボイス発行 可能 不可 買主の仕入控除可否 可能 不可 売却価格への影響 少 価格交渉の材料となる このように、インボイス制度は不動産取引の実務にも直接関わるため、売主・買主双方での理解と対応が重要です。
2025年の税制改正が不動産売却に与える影響
2025年には消費税や不動産税制に関する重要な改正が予定されています。特に注目すべきは、インボイス制度下での不動産売却に関する課税事業者選択の影響や、消費税還付の要件厳格化です。これにより、従来よりも売却時の消費税計算や申告の手続きが複雑になり、法人・個人事業主ともに慎重な対応が求められます。
主な改正点と注意事項は以下の通りです。
- 消費税課税事業者であるかどうかの確認強化
- 不動産売却時のインボイス発行義務
- 土地・建物按分計算の明確化と根拠資料の保存義務
- 消費税還付申告の審査強化
特に、土地と建物の売却時における消費税の按分計算については、国税庁のガイドラインやシミュレーションを活用して正確に行う必要があります。ミスがあると税務調査時に追徴課税のリスクが高まるため、適切な確認と準備が不可欠です。
将来の不動産売却戦略と消費税対応の考え方
今後の不動産売却戦略では、インボイス制度と税制改正を見据えた長期的な視点が必要です。節税対策・リスク管理の観点から、課税事業者の選択や売却タイミング、適切な申告・記帳体制の整備が重要となります。
長期的な戦略のポイントは次の通りです。
- 売却前に事業者区分を明確にする
- 土地・建物の価格按分計算を適正に行う
- インボイス発行体制を整備する
- 消費税申告・納付のスケジュール管理を徹底する
- 税理士など専門家への早期相談を検討する
不動産売却を検討する際は、下表のような主なチェックリストを参考に、事前準備を進めることが重要です。
チェック項目 対応状況 売主の課税事業者・免税事業者区分 インボイス発行登録の有無 土地・建物の価格按分方法の確認 申告・納付スケジュールの把握 税理士等専門家への相談 今後も不動産売却の消費税をめぐる制度は流動的です。新たな法改正や実務上の運用に柔軟に対応できるよう、最新情報の収集と備えを怠らないことが重要です。
会社概要
会社名・・・株式会社MINAMI
所在地・・・〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号・・・0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------
ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------