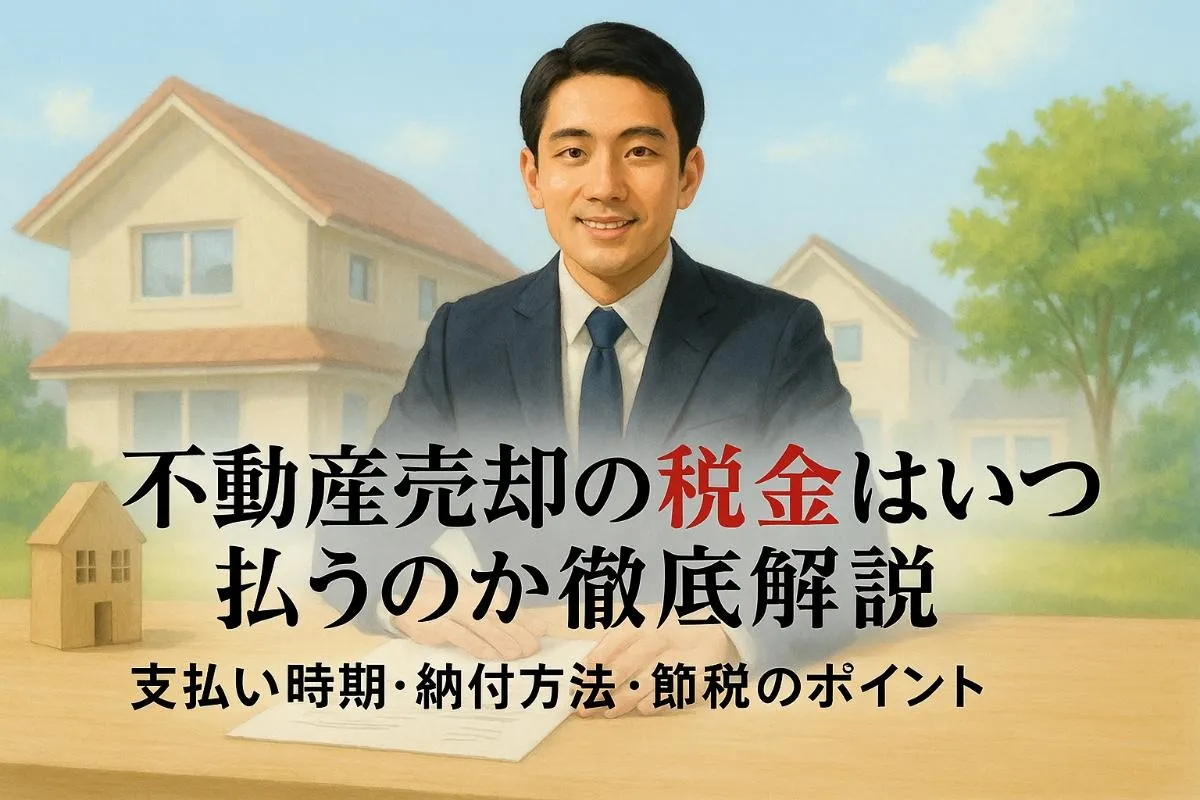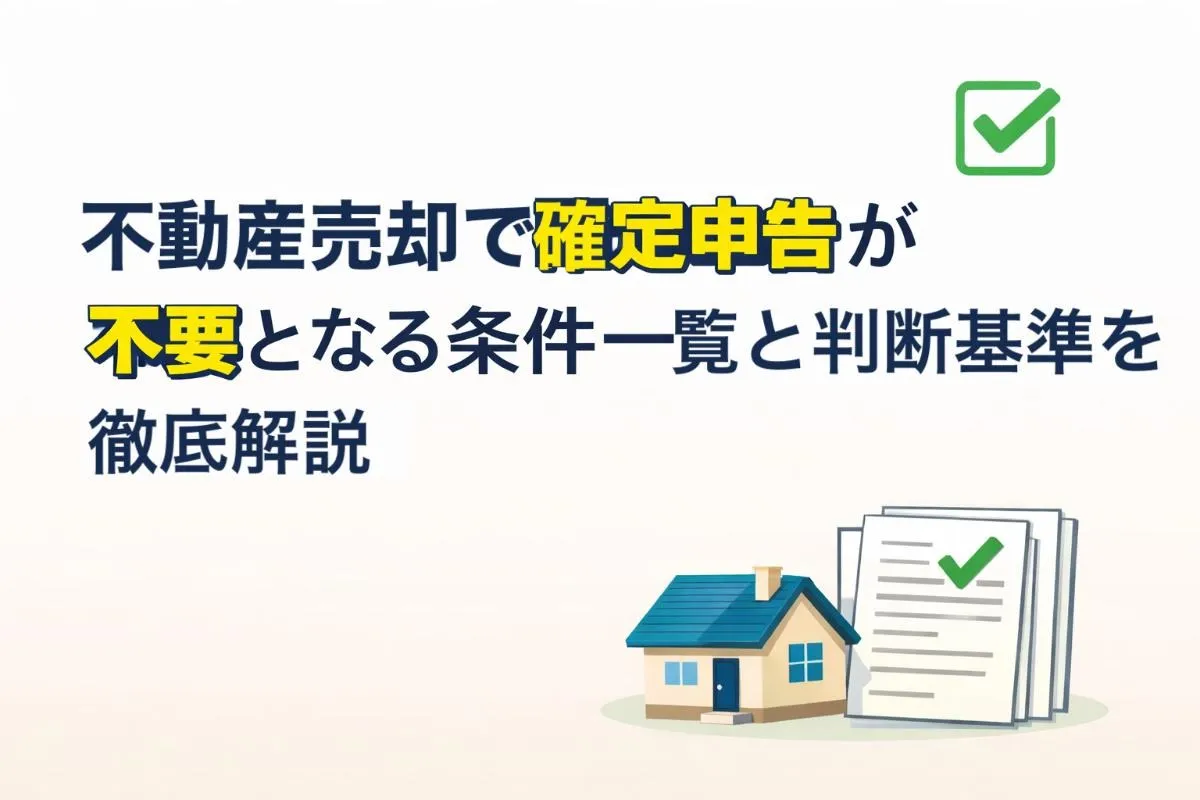不動産売却の税金はいつ払うのか徹底解説|支払い時期・納付方法・節税のポイントを事例付きで紹介
2025/10/03
「不動産を売却したら、税金はいつ、どのくらい払うのか?」
この疑問を抱えたまま契約や引き渡しを進めていませんか。実は、売買契約時の印紙税や登記の登録免許税、そして譲渡所得税や住民税など、支払いのタイミングや計算方法はそれぞれ異なります。不動産売却後は【翌年2月16日~3月15日】の間に確定申告を行い、譲渡所得税を納付。住民税はその後【6月】以降に納付書が届き、分割納付も可能です。
マンションや戸建て、土地の場合も税額は大きく異なり、売却価格や所有期間、特例の有無によっても負担が大きく変わります。例えば、5年超所有の長期譲渡所得税率は約20%、5年以下の短期譲渡所得税率は約39%と、税率だけでここまで差が出ます。
「知らなかった」では済まされない納税スケジュールの違いや、特例適用による節税チャンスも、事前に知っておくことで大きな損失回避につながります。
「納付書はいつ届く?」「相続や空き家の場合は?」「節税できる制度はある?」そんな不安や疑問も、この記事で一つずつクリアにしていきましょう。
しっかりポイントを押さえれば、想定外の出費や納付遅延で損をするリスクも減らせます。
本記事を読み進めれば、不動産売却にかかる税金の全体像と、あなたが「いつ」「何を」すべきかが明確になります。
目次
不動産売却にかかる税金の種類と支払いタイミングを徹底解説
売買契約時に発生する印紙税の概要と納付方法
不動産の売買契約においては、売買契約書の作成時に「印紙税」が発生します。これは国税の一種で、契約書という「課税文書」に対して課される税金です。印紙税の額は、契約書に記載された不動産の取引金額に応じて段階的に定められており、一定額の「収入印紙」を購入して契約書に貼付・消印することで納付します。
印紙税は、契約締結の時点で納付義務が発生し、その場で収入印紙を貼付・消印することで納付完了となります。税務署への申告や後日納付などの手続きは必要ありませんが、収入印紙の貼り忘れや消印漏れがあると「過怠税」(本来の印紙税額の3倍)が課される可能性があるため、十分な注意が必要です。
また、2024年3月31日までの契約には一部軽減税率が適用されていたため、時期によって税額が異なる可能性があり、最新の税制情報を確認することも重要です。不動産取引を円滑に進めるためにも、印紙税の納付方法や税額の確認は契約前にしっかり把握しておきましょう。
登記に伴う登録免許税の支払いタイミングと申請方法
不動産売却後には所有権移転登記が必要です。この際に発生するのが登録免許税です。登録免許税は売買代金や固定資産税評価額に基づき計算され、一般的に「固定資産税評価額×2%」が基準となります。登記申請時に一括で納付し、登記申請は通常司法書士に依頼しますが、本人による申請も可能です。
登録免許税のポイント
- 所有権移転登記:買主が負担
- 抵当権抹消登記:売主が負担するのが一般的
- 司法書士報酬が別途必要になる場合あり
正確な費用は事前に司法書士や不動産会社に確認しましょう。
譲渡所得税・住民税の支払いスケジュール詳細
不動産売却で利益が発生した場合、「譲渡所得」に対して所得税と住民税が課せられます。これらの税金は売却した翌年に確定申告を行い、所定の期間内に納付します。
- 確定申告期間:毎年2月16日~3月15日
- 所得税納付:確定申告時に一括納付
- 住民税納付:確定申告後、6月以降に納付書が届く
売却利益が3000万円以下の場合は「3000万円特別控除」などの特例が利用できるケースもあります。マンションや相続した土地の売却でも同様の流れですが、控除や税率については事前に確認しておくことが重要です。
所得税と住民税の支払い期限・納付方法の違い
所得税と住民税は納付時期や納付方法が異なります。所得税は確定申告時にまとめて支払う必要があります。住民税は申告内容をもとに市区町村から納付書が6月頃に届き、4回程度の分割納付が一般的です。
| 税目 | 納付時期 | 納付方法 |
|---|---|---|
| 所得税 | 2/16~3/15の確定申告時 | 金融機関窓口・e-Tax |
| 住民税 | 6月以降 | 納付書・口座振替 |
住民税は「普通徴収(納付書払い)」か「特別徴収(給与天引き)」を選択できますが、不動産売却による譲渡所得分は普通徴収が主流です。納付期限を過ぎると延滞税が発生するため、納付書が届いたら早めに支払いましょう。
譲渡所得税・住民税の計算方法と事例シミュレーション
不動産売却 税金 計算の基本プロセス - 売却価格、取得費、譲渡費用を用いた譲渡所得の計算方法
不動産売却時に発生する税金の計算は、まず譲渡所得を算出することから始まります。譲渡所得は、以下の計算式に基づきます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却価格 | 売買契約で決まった金額 |
| 取得費 | 不動産の購入時の価格+購入時の諸費用(仲介手数料、登録免許税など) |
| 譲渡費用 | 売却時にかかる費用(仲介手数料、印紙税、測量費など) |
譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
この譲渡所得に対して、所得税と住民税が課税されます。なお、居住用財産の3,000万円特別控除や特別控除の適用条件も重要なポイントです。正確な計算のためには、取得費や譲渡費用の領収書・資料をしっかり保管しておきましょう。
所有期間による税率の違いと短期・長期譲渡所得の税率比較 - 5年以内と5年超の税率と復興特別所得税の内訳を詳述
譲渡所得税は、不動産の所有期間により税率が異なります。所有期間が5年以下は短期譲渡所得、5年超は長期譲渡所得として区分されます。
| 区分 | 所得税 | 住民税 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|
| 短期(5年以下) | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 長期(5年超) | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
ポイント
- 所有期間は譲渡年の1月1日時点で判断。
- 復興特別所得税は所得税額の2.1%が加算されます。
- 節税を意識するなら、5年を超えて売却することで税率が半分近くに下がります。
譲渡所得 住民税の納付方法と分割納付の具体的なスケジュール - 特別徴収・普通徴収の違いと納付回数を説明
譲渡所得にかかる住民税は、申告後の翌年6月頃から納付が始まります。納付方法は以下2つです。
| 方法 | 内容 | 納付回数 |
|---|---|---|
| 普通徴収 | 納付書で自身で金融機関等に支払い | 年4回(6月・8月・10月・翌年1月) |
| 特別徴収 | 給与から天引き(会社員の場合) | 毎月の給与から自動控除 |
ポイント
- 不動産売却で生じた住民税は、原則として普通徴収(自分で納付)が選択されます。
- 納付書は自治体から送付されるため、期日を確認し遅延のないようにしましょう。
- 納付を忘れると延滞金が発生するため、スケジュールの把握が大切です。
不動産売却で税金がかからないケースと適用できる特例制度
不動産売却 税金 かからない場合の具体的条件 - 利益ゼロや特例適用で課税免除になるケースを詳細解説
不動産売却で税金がかからないケースにはいくつかの条件があります。まず、譲渡所得が発生しない、つまり売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて利益が出なかった場合、税金はかかりません。また、特定の特例制度を活用することで課税が免除または大幅に減額されるケースも存在します。
主な税金がかからない場合の条件を以下にまとめます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 譲渡所得がゼロまたはマイナス | 売却益が出なければ所得税・住民税は不要 |
| 3,000万円特別控除の適用 | マイホーム売却で一定条件を満たし、控除後利益がゼロになる |
| 相続税取得費加算の適用 | 相続した不動産を一定期間内に売却し、取得費を加算できる場合 |
| 譲渡損失の繰越控除を利用 | 売却損失が発生した際に他の所得と相殺できる |
上記のケースに該当すれば、不動産売却後の確定申告でも税金が発生しない、または納付額がゼロになることがあります。
マイホームの3,000万円特別控除の適用要件と注意点 - 適用対象の居住期間・譲渡条件をわかりやすく整理
マイホームを売却した際、最大3,000万円の特別控除が適用できる場合があります。この特例には明確な要件があり、条件を満たすことで譲渡所得税や住民税の負担が大幅に軽減されます。
3,000万円特別控除の主な適用要件は次の通りです。
- 自分が居住していた家屋や敷地であること
- 売却した年の前年及び前々年に同じ特例を使っていないこと
- 親子や夫婦など特別な関係者への売却でないこと
- 居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
控除を適用しても、利益が3,000万円を超えない限り税金はかかりません。なお、マンション売却や住んでいない家の売却でも条件を満たせば適用可能です。ただし、特例の併用や取得費の計算には注意が必要です。
相続した土地・家屋の売却特例 - 3年以内売却による取得費加算とその税務上の効果
相続で取得した土地や家屋を売却する場合、相続発生日から3年以内に売却すると「相続税額の取得費加算の特例」が利用できます。これは、相続時に支払った相続税のうち一定額を不動産の取得費に加算できる制度です。
この特例により、譲渡所得が圧縮され、所得税・住民税の負担が軽減されるメリットがあります。特に、相続税を多く支払った場合は、売却時の課税対象額が大きく減る場合があります。適用には期限や必要な書類があるため、早めの確認と準備が重要です。
その他の節税特例(買換え特例・譲渡損失の繰越控除など) - 利用条件と適用方法の概要
不動産売却で利用できる他の主な節税特例には、買換え特例や譲渡損失の繰越控除があります。買換え特例は、一定の要件を満たしたマイホームの買い替え時に、譲渡益への課税を将来に繰り延べできる制度です。
譲渡損失の繰越控除は、売却損失が出た場合に、他の所得と相殺したり翌年以降3年間まで繰り越して控除できる仕組みです。
主な特例の利用条件を表で整理します。
| 特例名 | 主な利用条件 |
|---|---|
| 買換え特例 | 居住用財産を売却し、新たに居住用不動産を取得 |
| 譲渡損失の繰越控除 | 売却損失があり、住宅ローン残高がある場合など |
それぞれの特例は申告方法や適用要件が細かく定められているため、専門家への相談や事前の準備が推奨されます。
不動産売却時の確定申告の実務ガイド
不動産売却 確定申告 必要書類一覧 - 登記事項証明書・譲渡契約書・収支内訳書などを具体的に列挙
不動産売却の確定申告を行う際は、必要な書類を事前に準備することが重要です。主な必要書類は次の通りです。
| 書類名 | 内容・用途 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 売却した不動産の登記内容を証明 |
| 譲渡契約書(売買契約書) | 譲渡価格・契約日を確認 |
| 収支内訳書 | 譲渡所得計算の根拠を明示 |
| 取得時の契約書・領収書 | 購入価格や取得費の証明 |
| 仲介手数料等の領収書 | 必要経費として計上 |
| 固定資産税納付書 | 年間の税負担を証明 |
| 印鑑証明書 | 売主本人確認用 |
| 住民票 | 居住状況の証明用 |
この他にも、特例適用時や相続物件の場合は追加書類が発生するため、事前確認をおすすめします。
確定申告のやり方と申告期限の詳細 - e-Tax利用のポイントや申告期間の注意点を明記
不動産売却後の確定申告は翌年2月16日から3月15日までが申告期間となります。申告方法は、税務署窓口・郵送・e-Tax(電子申告)の3つから選べます。
e-Taxを利用すれば、自宅から24時間申告手続きが可能です。マイナンバーカードやICカードリーダーが必要となるため、早めの準備が安心です。申告書類は、売却した翌年に作成し、譲渡所得の計算や必要書類を添付して提出します。
申告期限に遅れると延滞税や無申告加算税が課される場合があるため、スケジュール管理を徹底しましょう。
確定申告 不要な場合のケーススタディ - 利益が出ない場合や特例適用時の申告義務軽減条件
不動産売却で利益(譲渡所得)が出ない場合や、3000万円特別控除などの特例の適用で課税所得が0円になる場合、確定申告が不要となるケースがあります。
例えば、以下のような場合です。
- 売却価格が取得費や必要経費を下回るとき
- 居住用財産の3000万円特別控除を使い、譲渡所得が非課税となる場合
- 相続不動産の譲渡で特別控除が適用される場合
ただし、特例を利用する場合や損失の繰越控除を受けたい場合は、たとえ税金が発生しなくても申告が必要となるため、自己判断せず税務署や専門家に確認しましょう。
自分で申告する場合と専門家に依頼する場合のメリット・デメリット - 税理士相談のタイミングと費用感も説明
確定申告は自分で行う方法と、税理士に依頼する方法があります。それぞれのメリット・デメリットを整理します。
| 方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自分で申告 | 費用がかからない/申告内容を把握しやすい | 書類作成や計算が複雑/手続きミスのリスク |
| 税理士に依頼 | 正確な申告/節税アドバイスを受けられる | 費用(3~10万円程度)が発生 |
次のようなケースでは専門家への相談がおすすめです。
- 複数の特例を併用する場合
- 相続不動産や共有名義物件を売却した場合
- 譲渡所得の計算が複雑な場合
時間や手間、リスクを考慮して選択しましょう。
税金納付遅延リスクと納付忘れを防ぐための実践的対策
不動産売却後の税金納付は、期限を守ることが非常に重要です。納付遅延や納付忘れは延滞税や加算税といったペナルティの原因となるため、事前の対策が欠かせません。特に、不動産売却で発生する所得税や住民税は、売却後すぐではなく翌年に納付書が届くため、スケジュールをしっかり把握しておくことが大切です。
対策として、カレンダーやリマインダーアプリで納付予定日を管理したり、税務署からの通知を見落とさないようにしましょう。また、確定申告の時期や納付書の到着時期もあらかじめ確認しておくことで、納付忘れを未然に防げます。
不動産売却 税金 いつ来る?納付書到着時期の目安 - 納税通知の時期と納付書受取りまでの流れ
不動産売却による税金の納付書は、通常、売却した翌年に届きます。所得税の場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行い、その場で納付方法を選択します。住民税については、6月頃に市区町村から納付書が送付されます。
| 税金の種類 | 納付書到着時期 | 申告・納付方法 |
|---|---|---|
| 所得税 | 即時(申告時) | 確定申告提出時に納付金額が判明 |
| 住民税 | 6月頃 | 市区町村から郵送される納付書で納付 |
このように、税金ごとに納付書の到着タイミングが異なります。納付書が届いたら、忘れずに支払いを済ませることが大切です。
税金納付期限を守るための管理方法とリマインド術 - スケジュール管理のポイントと活用できるツール紹介
納付期限をしっかり守るためには、スケジュール管理が欠かせません。以下の方法がおすすめです。
- スマホのカレンダーアプリで納付日を登録
- リマインダー機能を活用して通知を設定
- 納付書が届いたらすぐ納付する習慣をつける
- 確定申告書類や納付書をまとめて保管する
特に、Googleカレンダーやスマートフォンの標準カレンダーは、通知設定や繰り返しリマインダーの利用が便利です。納付期限の1週間前や前日に通知を設定しておけば、うっかり忘れを防げます。
納付遅延時に発生する延滞税・加算税の計算例 - 遅延期間別のペナルティ金額イメージを提示
納付期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税が発生します。例えば、不動産売却による所得税や住民税で納付遅延があった場合、以下のようなペナルティが課されます。
| 遅延期間 | 延滞税率(目安) | 加算税(無申告加算税) |
|---|---|---|
| 2ヶ月以内 | 年2.5% | 15% |
| 2ヶ月超 | 年8.8% | 20% |
※税率は年度により変動します
たとえば、30万円の税金を2ヶ月遅れて納付した場合、延滞税は約1,250円(30万円×2.5%÷12×2ヶ月)、加算税は4万5,000円(30万円×15%)が追加で必要となります。納付が遅れると経済的負担が大きくなるため、早めの支払いが重要です。
納付期限を過ぎてしまった場合の対応策 - 相談窓口や分割納付の申請方法
万が一、納付期限を過ぎてしまった場合は、すぐに税務署や市区町村の窓口に相談しましょう。状況によっては分割納付や納税猶予を利用できる場合があります。
- まずは速やかに納付を済ませる
- 納付が困難な場合は、税務署や市区町村へ連絡し分割納付を申請
- 必要書類や申請書は各自治体のHPで確認可能
- 納税相談窓口では専門スタッフが対応してくれる
分割納付を希望する際は、収入や資産状況を伝える必要があります。早めの相談がスムーズな対応につながるため、納付遅延が判明した時点で行動しましょう。
相続不動産や住んでいない家の売却における税金の特殊事情
相続した土地 売却 税金の特例と節税ポイント - 3年以内の売却による取得費加算特例の解説
相続した土地を売却する際、「取得費加算の特例」が大きな節税ポイントとなります。これは相続税の申告期限から3年以内に土地を売却した場合、支払った相続税の一部を土地の取得費に加算でき、譲渡所得税を軽減できる制度です。主なポイントは以下の通りです。
| 特例名 | 条件 | 節税効果 |
|---|---|---|
| 取得費加算の特例 | 相続税申告期限から3年以内の売却 | 相続税の一部を取得費に加算し課税所得を減額 |
- 相続税が高額になったケースほど節税効果が大きい
- 売却スケジュール次第で税額に大きな差が生じるため、早めの検討が重要
この特例は一度しか使えず、申告期間を過ぎると適用できません。売却時期の見極めが節税のカギとなります。
相続した土地売却における譲渡所得税の計算方法 - 複雑な取得費計算と相続税控除の関係
相続した土地の売却における譲渡所得税の計算は、取得費や相続税の控除が絡むため複雑です。譲渡所得は「売却金額-取得費-譲渡費用」で算出します。
- 取得費:被相続人が土地を取得した際の費用+相続税の一部(取得費加算の特例適用時)
- 譲渡費用:仲介手数料や登記費用など
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 売却金額 | 実際の売却価格 |
| 取得費 | 購入時費用+相続税一部 |
| 譲渡費用 | 売却時の手数料等 |
過去の取得費が不明な場合、売却価格の5%を概算取得費として認められる場合があります。計算の際は、申告書類や領収書の保管が不可欠です。
住んでいない家の売却 税金の扱いと申告上の注意点 - 空き家特例の有無や譲渡損失繰越控除など
住んでいない家、いわゆる空き家を売却する場合でも税金の扱いには注意が必要です。一定の条件を満たすと「空き家の3,000万円特別控除」が利用でき、譲渡所得から最大3,000万円まで控除されます。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 被相続人が一人暮らし | 相続開始直前まで居住 |
| 昭和56年5月31日以前の建物 | 耐震基準適合等の条件あり |
| 売却期限 | 相続開始から3年目の12月31日まで |
- 控除適用には確定申告が必要
- 売却損が出た場合は、翌年以降の所得と相殺できる「譲渡損失の繰越控除」も検討可能
制度の適用条件や期限を正確に把握し、損をしないよう注意が必要です。
投資用不動産売却時の減価償却費考慮と税金計算 - 保有期間中の経費計上が税負担に与える影響
投資用物件を売却する場合、保有期間中に計上した減価償却費が譲渡所得税の計算に直接影響します。減価償却費分だけ取得費が減少し、その分譲渡所得が増加し課税額も大きくなります。
- 減価償却を多く行うと売却時の課税負担が増加
- 売却益が多い場合、短期・長期譲渡所得で税率が異なる点も要注意
| 減価償却の影響 | 内容 |
|---|---|
| 取得費減額 | 減価償却相当額を差し引く |
| 譲渡所得増加 | 売却益が課税対象として増加 |
| 税率 | 保有期間5年超で軽減あり |
投資用不動産の売却は税負担が大きくなる場合があるため、事前のシミュレーションと税理士への相談が重要です。
不動産売却 税金に関するよくある質問(FAQ)を記事内に自然に組み込み解説
不動産を売った時の税金はいつ払いますか?の詳細解説
不動産売却で利益が出た場合、税金の支払いタイミングは主に「所得税」と「住民税」で異なります。売却した年の翌年に確定申告を行い、申告期限は毎年2月16日から3月15日までです。所得税は申告時に一括納付となります。住民税は申告後、自治体から6月頃に納付書が送付され、分割払いも可能です。
主な支払いスケジュール
| 税目 | 納付時期 | 支払方法 |
|---|---|---|
| 所得税 | 翌年3月15日まで | 確定申告時納付 |
| 住民税 | 翌年6月〜 | 納付書で支払 |
この流れを把握しておけば、納付遅れによるペナルティも防げます。
家を売却した翌年に税金を払う理由の理解を深める説明
不動産を売却した年の税金を翌年に払うのは、確定申告制度によるものです。売却益が発生した場合、その収入は翌年2月16日から3月15日までに申告し、税額が確定します。そのため、売却から実際の納付までタイムラグが生じます。
理由のポイント
- 売却益は通常の所得と区別し、確定申告でまとめて申告
- 申告内容に基づき所得税を納付
- 住民税は自治体が申告内容をもとに6月頃に通知
こうした仕組みを理解することで、納税スケジュールの計画が立てやすくなります。
不動産売却 確定申告不要なケースの判定基準
全ての不動産売却で確定申告が必要なわけではありません。以下のケースでは確定申告が不要となります。
- 売却による利益(譲渡所得)が発生しない場合
- マンションや土地などの売却で「損失」が出た場合
- 住宅ローン控除など他に適用する控除がない場合
判定チェックリスト
- 売却価格が取得費+譲渡費用以下か
- 3,000万円特別控除などで利益がゼロ以下になるか
いずれかに該当すれば、確定申告不要となります。ただし、損失の繰越控除を受けたい場合などは申告が必要です。
譲渡所得税 計算シュミレーションの活用方法
譲渡所得税の計算は複雑ですが、国税庁などのシミュレーションツールを使うと簡単に目安を把握できます。
活用手順
- 売却価格・取得費・譲渡費用・所有期間を入力
- 3,000万円特別控除や相続・贈与の有無を選択
- 自動計算で税額・控除額が表示
主なメリット
- 計算ミスを防げる
- 節税の余地や控除適用可否が瞬時にわかる
- 所有期間による税率(5年超・5年以下)の違いも自動反映
不安な場合は税理士や専門家への相談もおすすめです。
不動産売却の税金対策と専門家活用の最適戦略
売却のタイミングを見極めて税負担を軽減する方法 - 所有期間調整や売却時期の最適化
不動産売却時の税金は、売却益に対して課税されます。特に重要なのは「所有期間」です。所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が高くなります。5年を超えると長期譲渡所得となり、税率が低減します。売却を急がず、所有期間を調整することで税負担を大きく軽減できる可能性があります。
所有期間別の税率比較
| 所有期間 | 所得税 | 住民税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|
| 5年以下 | 30% | 9% | 39% |
| 5年超 | 15% | 5% | 20% |
さらに、自宅売却の場合は3,000万円特別控除が適用されることもあるため、控除や特例を最大限活用できる売却時期を検討しましょう。
税理士相談や申告代行サービスの選び方と活用メリット - 費用対効果と相談時のポイント
税金対策や確定申告に不安がある方は、税理士など専門家への相談が有効です。複雑な譲渡所得の計算や控除適用など、プロのサポートでミスやトラブルを防げます。
税理士選びのポイント
- 不動産税務に強い専門家か
- 料金体系が明確
- 実績や口コミが良い
- 相談時の説明が丁寧でわかりやすい
税理士に依頼することで、確定申告書類の作成や提出をすべて代行してもらえるため、時間的な負担や申告ミスのリスクを軽減できます。費用対効果を考慮し、必要であれば積極的に専門家を活用しましょう。
不動産売却 税金シミュレーションツールの効果的な使い方 - 資金計画に役立つ活用法
不動産売却の税額は個別の状況によって異なるため、税金シミュレーションツールの活用が非常におすすめです。売却価格や取得費、経費、所有期間、各種控除を入力することで、概算の税額を簡単に算出できます。
シミュレーションの活用ポイント
- 事前に納税額を把握し、資金計画を立てやすくなる
- 節税策や控除適用の有無を確認できる
- 売却後の手取り額を正確にイメージできる
売却を検討する際は、複数のツールや国税庁公式ページも活用し、最新の税率や特例にも注意しましょう。
売却資金の納税準備と資金管理のコツ - 納付期限に合わせた計画的な資金確保術
不動産売却後の納税は、所得税は売却翌年の確定申告時(通常2月16日~3月15日)に納付し、住民税は6月頃から自治体より通知が届き納付します。納税資金を確保していないと、延滞税や加算税が発生するリスクがあるため、計画的な資金管理が必要です。
納税準備のポイント
- 売却益から必要な納税額を差し引いて資金をプール
- 資金管理用の口座を分けておく
- 納付期限をカレンダーやアラートで管理
- 資金繰りに余裕をもたせておく
計画的に準備することで、売却後の資金トラブルを未然に防ぎ、安心して次のステップへ進むことができます。
会社概要
会社名・・・株式会社MINAMI
所在地・・・〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号・・・0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------
ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------