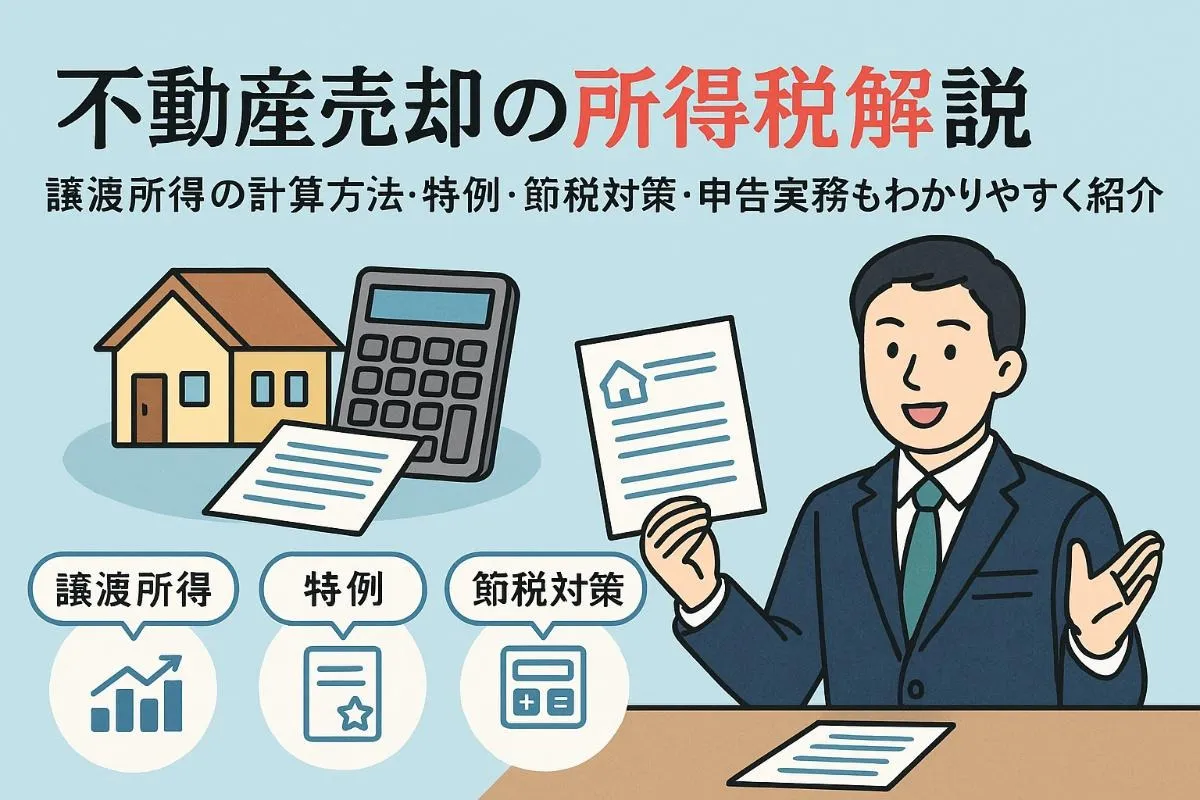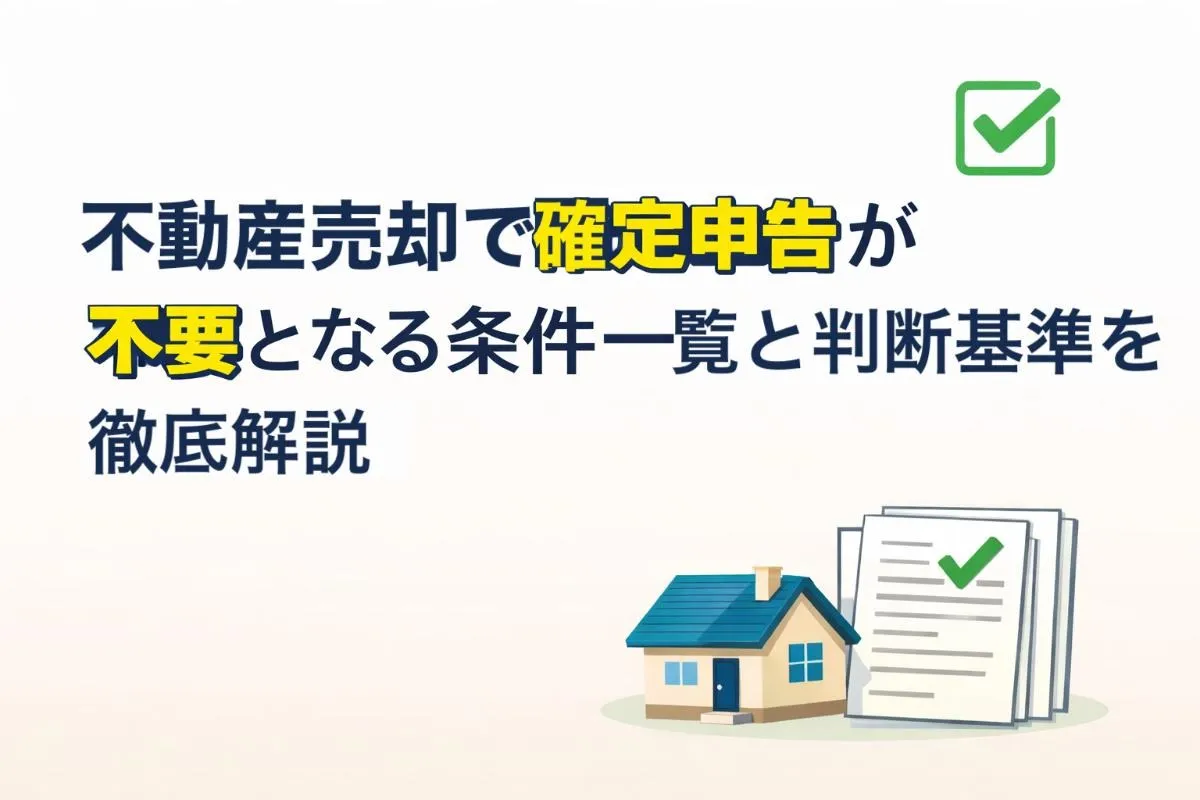不動産売却にかかる所得税の計算方法と節税対策を実例で解説
2025/09/06
「不動産を売却したとき、どれくらいの所得税がかかるのか分からず不安…」「税率や控除の仕組みが複雑で、損をしないか心配…」そんな悩みをお持ちではありませんか?
実は、【不動産売却による譲渡所得】には、所有期間が5年以下かどうかで税率が大きく変わります。さらに、3,000万円特別控除や取得費の計算方法によっても、納める税額が大きく変わるため、「きちんと知っておかないと数百万円単位で損をする」ことも珍しくありません。
本記事では「譲渡所得の計算式」「控除の適用条件」「確定申告の手続き」「最新の税制改正」まで、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。
知らなかったでは済まされない不動産売却の税金。大切な資産を守るために、今すぐ正しい知識を手に入れましょう。
目次
不動産売却にかかる所得税の基礎知識と税制の全体像
不動産売却に関連する税金の種類と違い
不動産売却時には主に「所得税」「住民税」「譲渡所得税」が課税対象となります。譲渡所得税は不動産を売却して得た利益(譲渡所得)にかかる所得税と住民税の総称です。課税対象は、売却価格から取得費や譲渡費用、控除額を差し引いた利益部分となります。事業用や居住用、相続した不動産によっても税金の種類や計算方法が異なります。
下記に主な税金の種類と違いをまとめます。
| 税金の種類 | 説明 | 課税対象 |
|---|---|---|
| 所得税 | 譲渡所得に対して課税される国税 | 譲渡所得 |
| 住民税 | 地方自治体に納付する税金 | 譲渡所得 |
| 印紙税 | 売買契約書に課される税金 | 契約書の作成時 |
譲渡所得税は所得税と住民税の合計であり、売却利益が発生した場合に納付義務が生じます。
譲渡所得とは何か?基本的な考え方と計算の流れ
譲渡所得とは、不動産の売却により得られた利益を指します。計算方法は以下の通りです。
譲渡所得の計算式:
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費+譲渡費用)− 特別控除
取得費には購入時の価格や仲介手数料、譲渡費用には売却時の仲介手数料や印紙税などが含まれます。特別控除の代表例として、「3,000万円特別控除」があります。
譲渡所得は所有期間によって短期と長期に分類され、それぞれ税率が異なります。
- 短期譲渡所得:所有期間が5年以下の場合。
- 長期譲渡所得:所有期間が5年を超える場合。
税率は以下の通りです。
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 30% | 9% |
| 5年超(長期) | 15% | 5% |
所有期間が長くなるほど税率は低くなります。適切な計算と控除活用が、税負担軽減のポイントとなります。
不動産所有期間の判定基準と税率適用のポイント
不動産の所有期間は、譲渡した年の1月1日時点での所有年数で判定されます。例えば、2019年3月に取得し2024年12月に売却した場合、2024年1月1日時点で5年未満のため短期扱いとなります。
所有期間の判定基準まとめ
- 取得日は登記簿上の取得日
- 売却日は売買契約日
- 所有期間は売却年の1月1日現在でカウント
所有期間が5年以内か5年超かで税率が大きく異なるため、売却タイミングの調整が節税対策となります。住民税も同様に所有期間で税率が変わるため、事前にシミュレーションを行い最適なタイミングを見極めることが重要です。
このように、所有期間や控除制度を正確に把握することで、不動産売却にかかる税金を適正に計算し、無駄な納税やペナルティを避けることができます。
不動産売却所得税の詳細な計算方法とシミュレーション活用
取得費・譲渡費用とは何か?計算に含める具体的費用の範囲
不動産売却時の所得税計算で重要なのが「取得費」と「譲渡費用」です。取得費は、売却した不動産を購入した際の価格に加え、購入時の仲介手数料や登録免許税、不動産取得税、建物の減価償却費などを含みます。実額が不明な場合、概算法として売却価格の5%を取得費とすることも可能です。譲渡費用には、売却時に発生した仲介手数料、契約書の印紙代、建物の取り壊し費用、測量費、売却のための修繕費などが含まれます。
下記の表で、主な費用の範囲を整理します。
| 項目 | 具体例 | 説明 |
|---|---|---|
| 取得費 | 購入代金・仲介手数料・登録免許税 | 土地・建物購入時にかかった実費 |
| 譲渡費用 | 売却仲介手数料・印紙代・修繕費 | 売却のために直接かかった費用 |
| 減価償却 | 建物部分のみ | 建物価値の減少分。所有期間に応じて計算し取得費から控除 |
取得費と譲渡費用を正確に把握することで、余計な税金を支払うリスクを減らせます。
譲渡所得の計算例(住宅・土地・マンション別)
譲渡所得の計算は、以下の式で求めます。
譲渡所得 = 譲渡価額 -(取得費+譲渡費用)- 各種控除
例えば、住宅を4,000万円で購入し、仲介手数料や登録免許税が200万円、売却価格が5,000万円、売却時の仲介手数料など譲渡費用が150万円の場合、計算方法は次の通りです。
- 取得費: 4,000万円+200万円=4,200万円
- 譲渡費用: 150万円
- 譲渡所得: 5,000万円-(4,200万円+150万円)=650万円
土地やマンションでも基本的な計算方法は同じですが、建物部分は減価償却を適用します。また、マイホームの場合は3,000万円特別控除が利用できることがあります。
主な控除制度も併せて確認しましょう。
| 種類 | 控除内容 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | 自宅売却時に最大3,000万円控除 | 一定の要件を満たせば適用可能 |
| 相続財産の取得費加算 | 相続税額の一部を取得費に加算 | 相続で取得し3年以内の売却など |
控除の適用によって税負担が大きく変わるため、必ず条件を確認しましょう。
計算ツールやシミュレーションの活用法と注意点
不動産売却所得税の計算は複雑な場合が多いため、国税庁や専門サイトの計算ツールを上手に活用しましょう。下記の流れで利用すると便利です。
- 売却価格・購入価格・諸経費を手元に用意
- 国税庁の「譲渡所得の計算シミュレーション」や不動産会社の計算ツールに入力
- 控除が適用できるか確認
ただし、ツールごとに入力項目や計算方法が異なる場合があるので、控除の適用条件や減価償却の計算方法は必ずご自身でも確認してください。
また、計算結果はあくまで目安です。実際の申告時には必要書類を揃え、税理士や専門家に相談することでトラブルを回避できます。不動産売却所得税の支払い時期や申告方法、住民税との関係にも注意しましょう。
正確な計算とシミュレーションを行い、余計な税負担を回避しましょう。
確定申告の手続きと納税の実務
不動産売却後の確定申告が必要なケースと不要なケース
不動産を売却した際には、所得税や住民税の申告義務が発生する場合があります。確定申告が必要になる主なケースは以下の通りです。
- 売却によって譲渡所得(利益)が発生した場合
- 特別控除(3,000万円特別控除など)を利用したい場合
- 相続した不動産を売却し控除・特例の適用を受けたい場合
- 非居住者が国内不動産を売却した場合
一方、確定申告が不要となる例は、譲渡損失が発生し、他の所得と損益通算しない場合や、譲渡所得が50万円以下で申告義務が生じないケースなどです。申告義務の有無は、所得の種類や金額、特例適用の有無で異なるため、事前確認が重要です。
確定申告の具体的な手続きと必要書類一覧
不動産売却後の確定申告では、正確な書類の準備と記載が求められます。主な必要書類は次の通りです。
| 書類名 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 譲渡所得の内訳書 | 不動産売却による所得の計算明細 |
| 売買契約書(写し) | 売却価格や契約日を証明 |
| 登記事項証明書 | 所有期間や物件情報の証明 |
| 取得費を証明する書類 | 購入時の契約書や領収書 |
| 譲渡費用の領収書 | 仲介手数料、登記費用など |
| マイホーム特例等の適用書類 | 3,000万円控除など特例適用時に必要 |
| 住民票の写し、本人確認書類 | 本人確認や住民税申告に必要 |
書類の不備は申告遅延や税務調査のリスクを高めるため、必要書類を一覧でチェックし、余裕を持って準備しましょう。
納税タイミングと方法(e-Tax・窓口・税理士依頼)
不動産売却に伴う所得税・住民税の納税タイミングは、原則として翌年の2月16日から3月15日までの確定申告期間中です。納付期限までに納税しないと延滞税や加算税が発生するため、注意が必要です。
納税方法には以下の選択肢があります。
- e-Tax(電子申告):自宅からオンラインで手続き可能。振替納税やクレジットカード納付も選べます。
- 税務署窓口:現金や納付書による支払いが可能です。
- 税理士依頼:自分で手続きが難しい場合は専門家に依頼することで正確かつ効率的に対応できます。
それぞれの方法にはメリット・デメリットがあるため、自分に合った納付方法を選択しましょう。納付期限内の手続き完了が重要です。
不動産売却に関わる特例・控除制度の詳細と節税対策
3,000万円特別控除の適用条件と活用法
不動産売却時に大きな節税効果が期待できるのが「3,000万円特別控除」です。これはマイホーム(居住用財産)を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。以下の条件を満たす必要があります。
- 売却した不動産が本人または家族の居住用であること
- 売却前に住まなくなった場合でも、住まなくなってから3年目の12月31日までに売却すること
- 親子や夫婦間など特別な関係者への売却は対象外
活用する際は、確定申告で必要書類を提出し、適用条件をすべてクリアしているかを確認しましょう。特に住民票や売買契約書、登記事項証明書が重要になります。注意点として、過去に同じ特例を利用した場合、一定期間は再利用できないため確認が必要です。
相続不動産売却時の特例・控除
相続した不動産を売却する際には、特別な控除や特例が適用できる場合があります。たとえば、相続した土地を取得から3年以内に売却する場合、一定の条件下で税金の軽減措置が受けられます。また、非居住者が相続不動産を売却する場合も、所得税や住民税の課税ルールに注意が必要です。
下記のテーブルで主なポイントを整理します。
| 特例・控除名 | 適用対象 | 主な要件 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続税の取得費加算 | 相続した不動産の売却 | 相続税を支払っている・相続開始から3年以内に売却 | 相続税の申告が必須 |
| 3,000万円特別控除 | 居住用不動産の相続後売却 | 居住実態・期間要件を満たす | 特例併用不可の場合あり |
| 非居住者の課税 | 日本国外在住の相続人 | 日本国内の不動産売却の場合、日本で課税される | 税率や控除に制限がある |
相続不動産売却では、税理士など専門家への相談も検討することで、不要な税負担を避けやすくなります。
節税のための売却タイミング調整と必要経費の適切な計上
譲渡所得税を軽減するには、売却のタイミングと必要経費の計上が重要です。所有期間が5年を超えると長期譲渡所得となり、税率が低くなります。売却する年の1月1日時点での所有期間を基準に判断しましょう。
効率的な節税のためのポイントは以下の通りです。
- 売却時期を調整し、長期譲渡所得の税率適用を目指す
- 仲介手数料やリフォーム費用、測量費など、譲渡に直接関わる費用を漏れなく必要経費に計上
- 必要経費の領収書や証拠書類をしっかり保管
また、ふるさと納税や他の所得控除制度と組み合わせることで、住民税や所得税の負担をさらに軽減できる場合もあります。税金シミュレーションツールを活用し、事前に売却後の税負担を試算することが推奨されます。
所得税がかからないケースと譲渡損失の扱い
譲渡所得税が発生しない典型ケースの紹介
不動産売却において譲渡所得税が発生しない典型的なケースとして、特に自宅売却時の「3,000万円特別控除」があります。この控除が適用されると、売却益が3,000万円以下であれば譲渡所得税がかかりません。また、譲渡損失が発生した場合も税金は発生しません。
| ケース | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | マイホーム売却時、売却益3,000万円まで控除 | 売却益が3,000万円以下なら税金ゼロ |
| 譲渡損失の発生 | 売却価格が取得費や経費を下回る場合 | 利益が出なければ課税なし |
| 相続不動産の特例 | 相続した不動産を一定期間内に売却した場合 | 条件を満たせば特別控除や軽減措置が適用される |
このような控除や損失の発生により、税金がかからない場合も多くあります。特に自宅や相続不動産の売却時は、適用条件をしっかり確認することが大切です。
損益通算と繰越控除の活用方法
不動産売却で譲渡損失が発生した場合、一定の条件を満たせば損益通算や翌年以降の繰越控除が可能です。
・損益通算
譲渡損失のうちマイホームに関するものは、給与所得や事業所得など他の所得と通算できます。これにより所得税や住民税の負担を減らせる場合があります。
・繰越控除
損益通算しても控除しきれない損失は、最長3年間にわたって繰り越して控除できます。毎年確定申告が必要ですが、税負担の軽減に有効です。
| 制度 | 概要 | 注意点 |
|---|---|---|
| 損益通算 | 他の所得と相殺し、所得税や住民税を軽減可能 | マイホームなど限定される |
| 繰越控除 | 控除しきれない損失を翌年以降3年間繰り越し可能 | 毎年確定申告が必要 |
損益通算や繰越控除を活用することで、譲渡損失が出ても税金面でメリットを得ることができます。
非課税とみなされる物件や売却形態の具体例
譲渡所得税が非課税となる物件や売却形態には、いくつかの具体的なケースがあります。
・自宅(マイホーム)売却
3,000万円特別控除や所有期間による軽減措置などが適用され、一定条件下で非課税となることがあります。
・相続した不動産の売却
相続物件は取得費加算の特例や3,000万円控除が利用できる場合があり、適用時は税負担が大幅に軽減されることがあります。
・法人所有物件の売却
法人が所有する不動産の売却は法人税の対象となるため、個人の譲渡所得税とは扱いが異なります。個人名義での非課税特例は適用されません。
| 売却形態 | 非課税・軽減の有無 | 主な適用条件 |
|---|---|---|
| 自宅売却 | 3,000万円特別控除等で非課税 | 自己居住用・所有期間条件 |
| 相続物件売却 | 控除・取得費加算等で軽減可能 | 相続後の一定期間内 |
| 法人所有物件の売却 | 個人の特例は適用外 | 法人税が課税対象 |
それぞれのケースで適用される特例や控除を正しく理解し、売却時の税金対策に役立てましょう。
不動産売却の所得税に関するよくある疑問
売却価格別の税額シミュレーション例
不動産売却時の所得税は、譲渡所得の計算方法に基づきます。譲渡所得は「売却価格-取得費-譲渡費用-控除額」で算出され、所有期間によって税率が異なります。以下に代表的なケースをまとめました。
| 売却価格 | 所有期間 | 取得費・譲渡費用・控除 | 譲渡所得 | 所得税・住民税合計(目安) |
|---|---|---|---|---|
| 50万円 | 10年 | 0円・0円・0円 | 50万円 | 約10万円 |
| 3000万円 | 10年 | 2000万円・100万円・3000万円特別控除 | 0円 | 0円 |
| 5000万円 | 3年 | 3000万円・200万円・0円 | 1800万円 | 約684万円 |
特に3000万円特別控除が適用されると、マイホーム売却時の税負担が大きく軽減されます。税金がかからない場合や、計算ツール・シミュレーションの活用も有効です。
所得税の支払時期と確定申告のタイミング
不動産売却による所得税や住民税は、売却した年の「翌年」に申告・納付が必要です。具体的な流れは以下の通りです。
- 売却した年の翌年2月16日~3月15日の間に確定申告を行います。
- 必要書類として、売買契約書・領収書・登記簿謄本などを準備します。
- 所得税は申告時に納付、住民税は翌年度に通知されます。
確定申告をしない場合、延滞税や加算税が課されることがあるため注意しましょう。自分で申告する場合やe-taxを利用する方法も増えています。
住民税・ふるさと納税・相続との関係性
不動産売却により発生した譲渡所得には、所得税だけでなく住民税も課税されます。また、ふるさと納税の控除上限額も変動するため注意が必要です。
- 住民税:譲渡所得が翌年度の住民税計算に反映されます。
- ふるさと納税:売却益が大きいと、寄付控除の上限金額が増加します。
- 相続と売却:相続した不動産を売却した場合も譲渡所得税の対象ですが、取得費や所有期間の特例、3年以内の売却での特別控除など、要件による軽減措置が存在します。
相続や贈与のケースは、取得費の引継ぎや課税関係に注意してください。
非居住者や法人所有の不動産売却時の税務
非居住者や法人が不動産を売却する場合、一般の個人と異なる税務ルールが適用されます。
- 非居住者:日本国内の不動産売却であれば所得税が課され、通常は源泉徴収(10.21%)が発生します。
- 法人:売却益は法人税の課税対象となり、税率や申告手続きも異なります。
特殊なケースでは、適用される控除や特例が異なるため、事前に税理士など専門家への相談をおすすめします。税務署への確認や最新の法改正情報のチェックも重要です。
最新の税制改正と今後の動向
2025年の譲渡所得税率や控除制度の変更点
2025年の不動産売却に関連する税制改正では、譲渡所得税率や控除制度にいくつかの重要な変更が施されました。
下記の表で、主な変更点と内容を整理します。
| 変更点 | 旧制度 | 新制度(2025年~) |
|---|---|---|
| 長期譲渡所得税率 | 15%(所得税)、5%(住民税) | 超富裕層に新税率制度 |
| 3000万円特別控除の適用条件 | 居住用財産の売却 | 相続空き家に係る場合に要件・控除額一部変更 |
| 相続不動産の譲渡所得税軽減 | 一定の控除 | 控除額・要件が変更 |
所有期間の判定や特例の適用には注意が必要で、特に相続や贈与を受けた場合は新制度での扱いをよく確認しましょう。また、新制度では必要書類や申告手順も一部変更されていますので、最新情報をもとに準備することが大切です。
税制改正に伴う申告・納税上の注意 - 新制度を踏まえた申告準備のポイント
税制改正に伴い、不動産売却時の確定申告や納税で注意すべき点が増えています。特に、申告期限や必要書類、控除の適用条件が変更されているため、事前の確認と準備が不可欠です。
- 申告期限の厳守:申告期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため、余裕を持って準備しましょう。
- 必要書類の最新化:売買契約書、登記簿謄本、取得費や譲渡費用の領収書、住民票など、必要書類は最新のものを準備してください。
- 控除適用の条件確認:3000万円特別控除や相続不動産の特例は、適用条件や手続きが厳格化されているため、必ずチェックしましょう。
最新の税制に対応した税務ソフトや計算ツールの活用も有効です。また、初めての方や複雑なケースでは税理士への相談を検討すると安心です。
今後予想される税務動向と不動産売却への影響
今後の税制改正では、不動産売却に対する課税強化や控除見直しの流れが続く見通しです。人口減少による空き家対策や相続税の課税強化が進む可能性が高く、売却時の税負担が増えるケースも考えられます。
今後の対策として、以下の点を意識しましょう。
- 売却タイミングの見極め:税率や特例の改正前後で売却時期を調整することで、税負担を抑えることが可能です。
- シミュレーションツールの活用:税額計算や控除適用のシミュレーションを事前に行い、納税資金を計画的に準備しましょう。
- 相続対策の強化:相続した土地や建物の売却では、特例や控除の要件が将来厳しくなる可能性があるため、早めの検討がおすすめです。
今後も税制改正動向を継続的にウォッチし、必要に応じて専門家の助言を取り入れることが重要です。
信頼性を高める公的データ・専門家監修情報の活用
国税庁・税務署発行データの紹介と活用法
不動産売却に関する所得税や住民税の正確な情報を得るには、国税庁や税務署が発行する公式資料の活用が不可欠です。特に、譲渡所得税の計算や特別控除の適用条件、確定申告のやり方などは、公式なガイドラインやFAQを参考にすることで、誤った解釈を避けられます。下記の表は、主な公的情報源とその活用ポイントをまとめたものです。
| 情報源 | 主な掲載内容 | 活用ポイント |
|---|---|---|
| 国税庁公式サイト | 譲渡所得税の計算方法、税率、控除制度 | 最新の税制改正や計算例を確認できる |
| 税務署窓口 | 個別相談、必要書類の案内 | 実際の申告手続きや疑問の解消に役立つ |
| 国税庁パンフレット | 申告書の記入方法、控除の詳細 | 初心者向けの分かりやすい情報が充実 |
公式データを基に手続きを進めることで、税金の過不足や申告ミスを未然に防げます。また、税制改正の情報も随時確認することが重要です。
不動産税制専門家・税理士の監修体制の説明
不動産売却に関わる税制は複雑で、所有期間や相続の有無によって税率や控除が大きく異なります。そのため、税理士や不動産税制専門家が監修した情報を参考にすることで、正確な判断が可能です。
- 不動産売却の譲渡所得税計算や控除適用の事例など、専門家が直接監修した情報は、信頼性が極めて高いです。
- 実際に税理士が監修した記事や解説では、相続した土地の売却や3000万円特別控除の適用事例など、具体的なケーススタディが紹介されており、実践的な参考になります。
- 各専門家の資格や所属、監修履歴が明記されている情報は、とくに安心して利用できます。
専門家監修の有無を確認し、より確実な情報を得ることが重要です。
相談窓口・専門家への問い合わせ案内
不動産売却や所得税の申告に関して疑問や不安がある場合は、専門の相談窓口を積極的に活用しましょう。
- 税務署の相談窓口では、申告書の書き方や必要書類、不動産売却による税金の計算方法について直接相談できます。
- 税理士事務所では、個別の状況に応じた節税対策や確定申告の代行も依頼可能です。
- 不動産会社の税務相談会やオンラインの税金相談サービスも利用できます。
| 相談窓口の種類 | 主なサービス内容 |
|---|---|
| 税務署 | 申告手続き全般、基本的な税務相談 |
| 税理士事務所 | 個別ケース診断、節税アドバイス |
| オンライン相談 | 気軽な質問、初回無料相談など |
疑問点は早めに専門家へ相談し、安心して不動産売却や確定申告を進められる体制を整えましょう。
不動産売却に関する所得税比較表とチェックリスト
所有期間別・物件種類別譲渡所得税率一覧表
不動産を売却した際の所得税率は、所有期間や物件の種類によって異なります。とくに所有期間が5年以下か5年超かで税率が大きく変わるため、事前の確認が重要です。
| 所有期間 | 種別 | 所得税率 | 住民税率 | 復興特別所得税 | 合計税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5年以下(短期) | 土地・建物 | 30% | 9% | 0.63% | 39.63% |
| 5年超(長期) | 土地・建物 | 15% | 5% | 0.315% | 20.315% |
| - | マイホーム控除 | 控除適用 | 控除適用 | 控除適用 | 控除適用 |
ポイント
- 所有期間5年を境に税率差が大きくなります
- 住民税も所得税同様に課税されるため、合計税率で確認することが重要です
- マイホームの場合は特例や控除が適用できる場合があります
特例・控除の適用条件と節税効果比較表
不動産売却時に適用できる特例や控除を活用すると、税負担を大幅に軽減できます。条件や節税効果を一覧で確認しましょう。
| 特例・控除名 | 適用条件 | 控除額・効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 3,000万円特別控除 | マイホーム売却、一定の居住要件あり | 最大3,000万円控除 | 親族などへの売却は対象外 |
| 買換え特例 | 売却後に新居購入、一定期間内に手続き完了 | 譲渡益を繰り延べ | 新居の要件・手続き期限に注意 |
| 相続財産の取得費加算 | 相続不動産の売却、相続税支払い済み | 取得費に加算し節税 | 売却期限や相続税の申告が必要 |
| 特定居住用財産の軽減 | 所有期間10年以上のマイホーム売却 | 税率軽減(最大14%等) | 長期所有・居住要件が必須 |
節税ポイント
- 3,000万円特別控除はマイホーム売却で最も利用される制度です
- 相続した土地の場合、取得費加算で税負担が軽くなるケースも多いです
- 特例ごとに適用条件や手続き期限が異なるので、売却前に必ず確認しましょう
確定申告の必要書類・ステップ別チェックリスト
不動産売却による所得税の申告には、多くの書類や手続きが必要です。申告漏れやミスを防ぐためにも、チェックリストを活用して準備しましょう。
必要書類リスト
- 売買契約書(コピー)
- 譲渡費用の領収書(仲介手数料など)
- 取得費証明書類(購入時の契約書・領収書等)
- 登記事項証明書
- 住民票(特例利用時)
- 確定申告書B・譲渡所得の内訳書
- 相続の場合は相続税申告書の写し
確定申告のステップ
- 必要書類をすべて揃える
- 譲渡所得を計算し、特例・控除の適用可否を確認
- 確定申告書類を作成(e-taxや税務署で提出可能)
- 申告期間内(2月16日~3月15日)に提出
- 税額に応じて納税
注意ポイント
- 必要書類が不足すると控除や特例が適用できない場合があります
- e-taxを利用すれば自宅から簡単に申告できます
- 相続・贈与が絡む場合は追加書類が必要になることがあります
不動産売却時の所得税対応は、事前の知識と正確な手続きが大切です。上記の比較表やチェックリストを活用し、安心して申告準備を進めましょう。
会社概要
会社名・・・株式会社MINAMI
所在地・・・〒250-0874 神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号・・・0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------
ミナミノイエ
神奈川県小田原市鴨宮343−2 A 203
電話番号:0465-43-9873
----------------------------------------------------------------------